病原性大腸菌O-157の予防とオーリングテストの活用
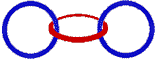
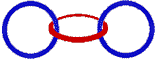
O-157は牛の腸内にもおり、国内の全国食肉衛生検査所協議会の全国調査によると、食肉牛4914頭のうち5頭からO-157が検出されたとされています。都立衛生研究所の甲斐明美主任研究員は、「牛を解体する時に、菌が肉の表面に付着している場合があり、生肉には気をつけた方がいい」と指摘しています。ことに米国では高率に検出され、米国で新鮮肉の培養をした結果では,牛肉3.7%、豚肉1.5%にO-157が検出されたとされています。
米国では毎年10,000〜20,000人が感染していると推定されており、200〜500人の方がなくなられています。
本年7月20日に神奈川県衛生部は、6月20日神奈川県の三浦市で小学4年生の男児から検出されたO-157の感染源が生の牛のレバーであると断定しました。
現在までに米国とカナダで20件以上の集団発生が確認されていますが、その事例のほとんどがハンバーガーまたは牛の挽き肉が原因食でした。加熱が不十分だったことが明らかになっています。冷凍でも菌は死滅しませんので、調理にあたっては中まで火が通るように十分に加熱してください。
米国ではキャンプなどで調理の際、加熱不足の不完全調理で感染するケースが報告されています。焼き肉料理をされるときは、照明が不十分で焼け具合がわからなかったり、先を急いで十分加熱されないうちに食べることのないようご注意下さい。
1992年10月米国メーン州で2才の幼児の死亡を含む出血性大腸炎患者4人の報告では、菜食主義者の人が感染したことと、飼っていた牛と堆肥から同じO-157が分離されたことより、牛の堆肥中のO-157で汚染された生野菜を食べて感染したと考えられています。
なお、牧場などで加熱消毒されていない牛乳をのむような場合は、 O-157の汚染に注意を払って下さい。
O-157の保菌動物や、患者さんの糞便から水を介しての2次汚染にも十分な警戒が必要です。
わが国で1990年9月上旬に埼玉県浦和市の幼稚園で腹痛や下痢、発熱を訴える園児が現れ、10月10日頃には同じ症状の園児が数10人になりました。溶血性尿毒症症候群で2名の園児がなくなられ、そのときの患者数は園児と家族、職員を合わせて319人に上りました。調査の結果、幼稚園のトイレタンクからの漏水によって井戸水がO-157などの病原性大腸菌に汚染されていることがあきらかとなり、この水を飲んだことにより感染が広がったと考えられています。
1991年の夏、アメリカのオレゴン州でO-157感染と、赤痢菌感染がほぼ同時に発生しました。質問表による調査で、患者さんはポートランド近郊にあるBlue Lakeという湖で水泳したことと関係が深いことがわかりました。湖の水泳場で糞便の汚染度を示す腸球菌が数多く検出されたことから、湖がO-157と赤痢菌を含む糞便の流入によって汚染され、水泳の際にその水が口に入り感染したものと考えられています。
本年、 堺市対策本部が市民を対象に実施した無料検便のうち、8月22日までに検査を終えた82,495人中1,093人からO-157が検出されています。
2次感染に十分な注意が必要と思われます。
食品を扱うときは、手や調理器具を十分に流水であらい菌の付着の恐れをなくすことが必要です。
汚染の恐れのある食品や飲料水は十分加熱する事が大切です。菌は75℃1分で死滅します。内部まで十分熱が通るように調理して下さい。
患者さんの下痢便の1滴には約100万個の細菌が含まれているといわれております。感染の恐れのある方の糞便や糞便に触れたものは十分な注意の元に衛生的に処理してください。水泳や入浴を控え、身体を洗うときはシャワーで流すようにされるのが望ましいかと思います。
症状のない方も、トイレのあとや汚物を処理された後は、手指を十分に流水で洗うようにいたしましょう。
殺菌効果の高いエチルアルコールを調理器具などの消毒に用いる方法もあります。霧吹きなどで吹きかけたり、脱脂綿などにしみ込ませたりして使います。すぐ蒸発する上、口に入っても少量では害がないため、まな板などの消毒に適しています。「消毒用アルコール」の名称で薬局・薬店で購入できます。価格は500ml入りのびんで800円前後のようです。
O-157と接触しないようにすることが最も安全な方法ですが、プールに行ったときや、なまものを食べた場合にどうすればよいのでしょうか。
体内に菌が入っても、腸の粘膜に菌が生きてとどまらなければ発病にはいたらないと思われます。胃腸の粘膜を荒らさないように、普段から節制しておくこと、免疫が低下しないように肉体的疲労や精神的ストレスを避けることなどが大切かと思います。逆に疲れているときは食事に十分注意が必要です。
また、冷たい食べ物や飲み物は、胃腸の働きを一時的に悪くしてしまいますので、控えるようにして下さい。
体内に侵入してしまった菌をやっつけるいい方法はないのでしょうか?
昭和大学医学部細菌学の島村忠勝教授らの実験によると、緑茶や紅茶は食中毒の原因となる細菌を殺したり、毒素の働きを抑える作用があることがわかっています。お茶の渋みを出しているタンニンの主成分であるカテキンという物質が効果を発揮していると考えられ、なかでもエピガロカテキンガレートという成分が着目されています。日本茶の中では番茶や煎茶がよく効くようで、ふつうの濃さで十分です。なお、コーヒーにはこの作用はほとんどないということです。
緑茶や紅茶は、細菌だけでなく、マイコプラズマやウイルスを抑える作用が実験で認められています。インフルエンザや風邪の予防にうがいとして使うこともでき、出がらしのお茶でも有効ということです。
筆者がオーリングテストを使ってウイルスや細菌に効くかどうかをテストしてみたことがありますが、かなり少ない量で有効と思われました。O-157に対してのテストでも比較的少量のお茶や緑茶の葉で毒性をキャンセルし、その効果に個人差がほとんど見られないことから、直接的な抗菌作用があるものと思われました。
食事中にお茶を飲むことは食中毒を防ぐ有効な方法で、日本人としては習慣の一部であり、実行しやすい方法だとおもいます。《参照》
オーリングテストで調べたところ、わさびや生姜(しょうが)、紫蘇(しそ)の葉である蘇葉(そよう)も効果があると思われました。さしみや寿司を生で食べるための生活の知恵といえるでしょう。紫蘇は他の生薬と配合されて漢方薬として用いられる香蘇散(こうそさん)や参蘇飲(じんそいん)などでも有益な反応が見られました。わさびはや生姜は量が多くなるとかえって有害な反応が見られますので、適量をとることがたいせつです。また、それらの効果には個人によって差が認められました。そのことから推察して、直接的な作用だけではなく、免疫系を介しての作用が加わっているものかと思われます。ちなみに筆者は、すでにウイルス性や細菌性の胃腸炎を起こした患者さんに、よく参蘇飲のエキス剤を用いますが、通常の方法より短期間で病状がよくなることを経験しています。 日本で古くから民間薬としてよく用いられてきた黄柏(おうばく)はミカン科のキハダの樹皮をはいで作られますが、ベルベリンというアルカロイドを成分として持っています。ベルベリンは赤痢菌・コレラ菌などに対する抗菌力や腸内細菌が有毒物質を作り出すのを抑える作用が認められています。「陀羅尼助(だらにすけ)」や「百草」、「煉熊(ねりぐま)」など、胃腸の常備薬として家庭においてある方も多いのではないでしょうか。オーリングテストで調べたところ、予防的には通常使用量の10分の1程度でも効果があるものと考えられました。
日本で古くから民間薬としてよく用いられてきた黄柏(おうばく)はミカン科のキハダの樹皮をはいで作られますが、ベルベリンというアルカロイドを成分として持っています。ベルベリンは赤痢菌・コレラ菌などに対する抗菌力や腸内細菌が有毒物質を作り出すのを抑える作用が認められています。「陀羅尼助(だらにすけ)」や「百草」、「煉熊(ねりぐま)」など、胃腸の常備薬として家庭においてある方も多いのではないでしょうか。オーリングテストで調べたところ、予防的には通常使用量の10分の1程度でも効果があるものと考えられました。
また、ベルベリンの含量の多い生薬としてキンポウゲ科のオウレンの根茎の黄連(おうれん)があります。これはよく漢方薬にも配合され、半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)・三黄瀉心湯(さんおうしゃしんとう)・胃苓湯(いれいとう)・黄連湯(おうれんとう)・黄連解毒湯(おうれんげどくとう)などが、胃腸疾患に体質に応じて用いられています。中でも黄連解毒湯(おうれんげどくとう)には黄檗(黄柏・おうばく)も配合されており、通常は体力のある人ののぼせ症状などに用いられますが、吐血・下血に著効を示す場合があり、大腸の炎症が激しく出血性腸炎をおこしている場合に有用性があるのではないかと思います。
予防としては、まず菌を避けること。次に胃腸の働き、身体の抵抗力を落とさないようにすること。その次の策として、効果とその用いやすさからいっても、食事中に温かいお茶を飲むことをお勧めします。
おなかの中で解毒するより、やはり菌を避けることが最も肝要です。かといって、目の前の食品から細菌を肉眼で見つけるわけにはいきません。細菌を培養して調べるのには数日が必要です。それまで食べるのを待ちますか?
米国ではO-157を検出するキットがいくつかの会社から発売されています。18〜24時間で検出が可能で、1検体あたり980〜1,730円かかります。
本年7月1日に、大阪府立大農学部の獣医公衆衛生学楠博文助手が、蛍光抗体を使って90分以内でO-157を検出する方法を発表されました。水を分析の対象として、検出には1ml中に数千個の生菌が必要であるとのことです。
いずれにしても、誰もが手軽に実施できるという方法ではありません。
オーリングテストの共鳴現象を使った存在診断を用いると、その場で即座に水でも食べ物でも感度よくO-157をスクリーニング(選別検査)する事が可能です。同一物質間で筋力低下現象が起こることを利用して、手に持ったサンプルと同じものが指さした対象物に存在しているかどうかを判定します。
0-157の存在の推定するには、共鳴現象のコントロール物質として0-157の細菌をプレパラートに固定したサンプルを用いる方法と、O-157免疫血清をサンプルとして用いる方法とがあります。筆者が調べたところでは、前者は病原性大腸菌O-157に著明な筋力低下をおこしますが、O-157以外の大腸菌にも交差共鳴反応をおこし、少し筋力低下現象が認められました。後者は他の大腸菌には反応せず、O-157の細菌に特異的に共鳴反応を示しました。後者の場合は感染の危険がなく、標本の作成や使用段階で安全に用いることができ、またO-157にねらいを定めて調べるのに適切だと思われます。筆者は、デンカ正研株式会社(東京都中央区日本橋兜町12番1号)の病原大腸菌免疫血清「正研」(体外診断用医薬品)を一滴スライドガラスに滴下し、カバーガラスで封入したものを作成して0-157を調べるサンプルとして用いています。
いろいろな食中毒原因菌のサンプルを用意することができると、食品の細菌汚染をより具体的に調べることができます。
実際の食中毒発生例で、保健所の方と協力して、患者の糞便や患者の食べた食品を調べたことがあります。オーリングテストで迅速に感染源や菌種を推定し、早急に被害の拡大を防ぐことができました。オーリングテストの結果は、何日も後から帰ってきた実際の細菌培養の結果とほぼ一致しておりました。
オーリングテストで体外の物質と手に持ったものとの間の共鳴現象を調べることは、ノイズの混入などにより判定を誤る可能性が高く、精度を高めるのに熟練を要します。純粋なサンプルを用意する必要もありますし、また、その結果が正しいかどうか現代科学の方法論で確認をしていく必要があるかと思います。しかし、適切に調べることができるならば、簡便かつ迅速な食品の検疫のスクリーニングとして、威力を発揮するものと思います。
オーリングテストの基本的な方法を習得されているのなら、オーリングテストを適切に用いることによって、食中毒を未然に防ぐことができます。
被験者の2本の指で作ったオーリングを選択し、反対の手でその人が食べる予定の食品を指さして、力が弱くなっていないかをチェックします。力が抜けてオーリングが開く場合は、その人にとって有害な食品であることが疑われますので、その食品は食べない方が良いと思われます。
この簡便な検査で、食中毒が予防できるのです。
もちろんテストに習熟し、正確なテストができた上でのことですが、テストの結果の解釈には十分留意する必要があります。
かりに指の力が抜けても、すぐに食品に有害物質が混入していると判断してはいけません。その人が食事をした後の場合は、胃腸の中に同じ食品があるため共鳴現象によって力が抜けてしまうことがあるからです。また、有害性の理由として、その人の病気や体調によるものも考えられます。例えば胃潰瘍の人は刺激物でオーリングの力が抜けるでしょうし、糖尿病の人はカロリーが多いもので力が抜けてしまうでしょう。対象物の量が多すぎても有害と判定されてしまうことがあります。
もし、食品自体に問題があるかどうかを知りたければ、複数の健康な人で、一回摂取量を対象として調べることが望まれます。
また逆に、指の力が抜けなかったからといって、その食品が汚染されていないとはいえません。その人の免疫が強いと少量の菌が混入していてもオーリングが開かないことがあるからです。食事をする本人以外で検査する場合、特に乳幼児や病気の方、お年寄りなど、免疫が弱っている人が食べる場合はそのことに十分注意して下さい。
牛の腸内にO-157を保菌している場合があることから、最初の感染源としてホルモン料理や挽き肉、保菌率の高い国から輸入した冷凍食肉やハンバーグ、牛糞から堆肥や水を介して汚染された生野菜などを注意する必要があろうかと思います。
オーリングテストに熟練している方は、汚染の有無を調べてみて下さい。しかし、オーリングテストの結果だけで断定してはいけません。公衆衛生領域の方と協力し、培養検査などで確認することが大切です。汚染の恐れのある食品をオーリングテストでスクリーニングして見つけだすことができれば、効率の良い迅速な対応が可能となり、被害拡大の防止に貢献できるのではないかと思っています。
個人レベルで食中毒を防ぐことが大切な時代になってまいりました。オーリングテストで有害な反応が見られたからといって不安をかりたてたり、反応がないからといって安全だと過信しないようにして下さい。五感で得られた情報と、正しい知識と経験をふまえた上で、オーリングテストの結果を判断材料の一つに加えてみて下さい。オーリングテストの活用で、より安全で健康な生活をおくることができるようになるでしょう。
展示および記載責任者: 山本重明 Shigeaki YAMAMOTO