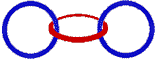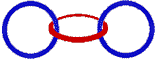情報クリップエッセンス
2002年3月号
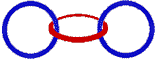
Essence of Cliped Information
March, 2002
最近のニュースや論文などから、健康に暮らすために役に立つ情報をまとめています。有害なものを避けて有益なものを取り入れ、身体のしくみを活かして下さい。
2002年03月27日 展示
目次
各種報道記事、医学関係紙、その他関連サイトの情報をもとにしております。
(※は筆者のコメントです)
有害物質
一般に有害とされる事項に分類されるものの情報です。
対策についての情報も含んでいます。
微生物・生物
- 愛知県瀬戸市の公立陶生病院で生まれた新生児7人が、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)に院内感染し、昨年10月20日ごろから11月5日ごろまでにブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群を発症していたことがわかりました。表皮がやけどのようにはがれる症状が起きたなどの訴えが相次ぎ、検査をするとMRSAが検出されました。
- 院内感染の主要な原因菌の一つ、黄色ブドウ球菌(Staphylococcus
aureus)に対するワクチンが、透析患者1800人を対象としたプラセボ対照無作為化臨床試験で予防効果を実証しました。米国Kaiser
Permanenteワクチン研究センターのHenry Shinefield氏らは、黄色ブドウ球菌の周囲を覆う多糖類(ポリサッカライド)から作ったコンジュゲート・ワクチン「StaphVAX」(米国Nabi社製)を用い、透析患者に対する予防効果を調べました。その結果、投与後3〜40週で、プラセボ群(906人)では26人が菌血症を発症。ところが、ワクチン投与群(892人)で菌血症を発症したのは11人と有意に少なく、相対リスクが56%(95%信頼区間:10〜81%、p=0.02)減少することが判明しました。ただし、ワクチンによる予防効果は40週以降から低下しました。
- 新潟大学医学部付属病院で、患者18人が抗菌薬の効かない「多剤耐性緑膿菌」に院内感染し、うち1人は同菌が主原因で死亡していたことが明らかになりました。00年1月から昨年6月までの間に男性17人、女性9人の計26人の患者から同菌が検出され、このうち昨年5月に死亡した白血病の30歳代の男性患者ら18人が遺伝子解析から院内感染と断定されました。
- 名古屋市立大病院(同市瑞穂区)で2000年11月から12月にかけ、小型球形ウイルス(SRSV)による院内感染で、子供の入院患者や職員ら75人が急性腸炎を発症していたことがわかりました。発症者はいずれも下痢やおう吐などの症状が1〜4日続いたということです。
- 採血や点滴など血管に針を刺す処置時に、使い捨ての手袋を使っている医療スタッフは、63人中わずか3%しかいないことが、川崎医大病院(岡山県倉敷市)の高度救命救急センター内で実施した抜き打ち調査でわかりました。肝炎ウイルスなどに汚染された血液に触れると、そのスタッフが感染する、スタッフを介して他の患者への院内感染を起こす、の二つの危険性があります。とくに救命救急部門は、どんな感染症にかかっているかわからない患者が搬送されることが多く、感染の可能性は高くなります。同センターが、対象を病院全体に広げ、医療スタッフ544人に手袋を使わない理由をアンケートしたら、「時間がない」が86%、「習慣がない」が85%、「細かい作業がしにくい」が73%でした。
- 院内感染が起きたとき具体的にどう対処したらよいかを分かりやすく示した手順書を、厚生労働省の研究班がまとめました。食品の衛生管理は、総合衛生管理製造過程(HACCP=ハサップ)により、病原菌や化学物質などの汚染を除く対策がとられています。手順書はこれを導入。病原体が、外科や内科の病棟で患者のたんから検出された場合の対処や患者に注射するときなどの注意をあげました。手順が守られているかどうかをチェックする表もつけました。例えば、多くの抗生物質が効かないメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)が一般病棟の患者の便から見つかった場合、個室に移してほかの患者との接触を避け、診察や処置は最後にする――などです。
- 大都市の噴水や人工滝といった水景施設の2割で肺炎などを起こすレジオネラ菌が増殖していることを大阪府立公衆衛生研究所と横浜市衛生研究所が突き止めました。霧状になった水を子どもや高齢者らが吸い込むと発病する危険性があり、「水温が20度を超す5月ごろから菌が増殖する。適切な管理と消毒が必要だ」と研究者は指摘しています。両研究所は大阪府と横浜市で一昨年9〜10月、公園やショッピングセンターなどの屋内外に設けられた水景施設82か所を調査しました。そのうち、15か所で100ミリ・リットルあたり10個以上の菌を検出。すぐに消毒を行う必要のある目安とされる100個以上検出された施設は8か所ありました。最高は大阪府内のビル敷地の噴水で6300個でした。米カリフォルニア州のホテルでは1988年、ロビーの噴水近くで食事をした34人が発病しています。
- 世界保健機関(WHO)は結核対策国際会議で、「BCGの接種は乳幼児期に1回だけ」とする勧告を出しました。BCGは子どもの重い結核を防ぐ効果があり、日本では現在、結核予防法で、ツベルクリン反応が陽性にならない限り、0〜4歳、小学1年、中学1年の時などに接種することになっていますが、複数回接種すれば効果が高まるのか疑問視されていました。東アジア・オセアニアの37カ国・地域の中で、BCGを複数回接種しているのは日本だけで、実質上、日本に向けての勧告となります。
- 梅肉に、胃や十二指腸かいようの原因とされ、胃がんとの関連も指摘されるヘリコバクター・ピロリ菌の増殖を抑制する効果があることが、和歌山県立医大の宇都宮洋才講師らのグループの研究でわかりました。宇都宮講師らは、ピロリ菌を培養した試験管内に、梅肉エキスの希釈液を加え、24時間後のピロリ菌の増殖数を比較。その結果、濃度1%の梅肉エキスを加えた場合、何も加えない場合の約50分の1に抑制できました。濃度を高めると、さらに抑制効果は高まった。また、ピロリ菌への感受性が高い特殊なネズミ、スナネズミを使った実験でも、梅を食べさせると感染を抑制できることが確認できたということです。
- 今冬にインフルエンザ脳炎・脳症で死亡した小児のうち4人が、脳炎・脳症を重症化すると指摘され小児への使用中止措置がとられている一部の解熱剤を、医療機関によって処方されたり、患者側の自己判断で服用したりしたケースだったことが、厚生労働省研究班の調査でわかりました。アスピリンなどサリチル酸系解熱剤と、「ジクロフェナクナトリウム」(※ボルタレンなど)という成分を使った解熱鎮痛剤はインフルエンザや水痘など、ウイルス性の病気の小児に投与しないこととされています。このほか「メフェナム酸」(※ポンタールなど)という成分の解熱鎮痛剤も、小児のインフルエンザによる発熱には使用しない措置がとられています。同省インフルエンザ脳炎・脳症研究班(班長、森島恒雄・名古屋大医学部教授)が、今シーズンの脳炎・脳症の患者として報告した17例中4例が措置が守られなかったとみられるケースで、いずれも死亡例でした。医療機関で薬を処方されたのは2例。このうち7歳の女児は、サリチル酸の入った総合感冒薬とジクロフェナクナトリウム、メフェナム酸の3種類、4歳の女児はメフェナム酸のみを処方されていました。2人とも実際に服用したかどうかは不明ですが、同省は「処方すること自体が問題」としています。残る2例では、6歳と8歳の女児が、何らかの理由で家庭にあったジクロフェナクナトリウムを服用していました。
- インフルエンザワクチンを受けると、インフルエンザだけでなく、脳梗塞も予防できる可能性が出てきました。フランスで60歳以上の高齢者を対象に行われた研究で、脳梗塞を起こした人では、インフルエンザワクチンの接種率が低いことがわかったためです。脳梗塞予防にワクチンが“効く”理由は不明だが、脳梗塞の発症には何らかの感染症が関与しているとの説があり、研究グループは「インフルエンザを予防することで感染症にもかかりにくくなったためでは」と説明しています。フランスDenis
Diderot大学附属Bichat病院のPhilippa Lavallee氏らは、脳梗塞や心筋梗塞などの「動脈硬化性疾患」で、クラミジアなどの感染症による炎症状態が続くことが、発作の引き金になるとの証拠が揃いつつあることに注目。インフルエンザの流行シーズンに、脳梗塞で病院に運ばれてきた高齢者90人と、年齢や性別、高血圧などの病歴などをマッチさせた一般市民180人とで、インフルエンザワクチンの接種率を比較しました。すると、一般高齢者のワクチン接種率が59.4%だったのに対し、脳梗塞を起こした人のワクチン接種率は46.7%でした。統計学的に検討すると、インフルエンザワクチンを受けた人では、受けなかった人よりも脳梗塞を起こす確率が2分の1になることがわかりました。
- 米国の科学者で組織する米科学アカデミー傘下の医学研究所(IOM)は、子どもの予防接種と、インスリン依存症糖尿病や髄膜炎、肺炎などの感染症の発病の間には「関係がない」とする報告書を発表しました。IOMの委員会は、免疫のかく乱などによって起き、子どもや未成年に多いインスリン依存型糖尿病と予防接種の関係を調べた8種類の過去の研究を洗い直しました。この結果、予防接種との関連は無関係との結論に達しました。かぜや中耳炎、髄膜炎、肺炎などの感染症についても調べましたが、関連性は見つかりませんでした。IOMではぜん息などのアレルギー疾患についても調査しましたが、現時点では明確な結論は出せないとしました。IOMは昨年、はしか、風疹、おたふくかぜの3種混合ワクチンと自閉症の関連についても調査、無関係との結論を発表しています。
- 「非加熱の血液製剤」投与が確認された血友病以外の患者のうち、半数にC型肝炎ウイルスの感染歴があり、27%からはウイルスが検出され感染が持続しているとの調査結果を、厚生労働省が発表しました。厚労省は昨年、1970〜80年代に非加熱製剤を血友病以外の患者に投与した可能性がある805の医療機関名を公表、検査を呼び掛けていました。昨年3月から7月にかけて検査した9680人のうち、調査に同意した9214人が対象。血友病以外で非加熱製剤投与が確認された患者は132の医療機関で計404人に上り、感染歴を示す抗体陽性者は52%の210人。遺伝子レベルの検査でウイルスが検出され、経過観察や治療が必要とされたのは27%の109人でした。29歳以下が64人と半分以上を占め、投与目的は新生児出血症の治療が179人で最多でした。
- 世界でHIV(エイズを起こすウイルス)に感染している推定5000万人の人々のおよそ半分は男性で、その70%がセックスを通して感染したものと見られています。40以上にのぼる研究成果をよく調査した結果、オーストラリアの研究者達は、HIVウイルスがペニスの包皮の内部表面に存在する特定の細胞(HIVレセプターを持っているラングハンス細胞)から感染するということを報告しました。男性の割礼は、この内部表面のHIVレセプターの大部分を取り去り、重要な防御対策になり、2倍から8倍HIVに感染る可能性が低くなるということです。
- 厚生労働省は、海外で売血血液を使って製造、輸入された血液製剤のラベルに「非献血」との表記を義務付ける方針を固めました。国内で製造される血液製剤はすべて献血でまかなわれており「献血」と表記されていますが、輸入製剤は献血か売血かを区別する表記がないのが実情で、患者側が「輸入の血液製剤についても売血か献血かを明確にし、投与の際に献血血液で作られた血液製剤を選択できるようにするべきだ」と要望していました。売血の場合も、血液製剤の製造過程でエイズや肝炎のウイルスを除去したり感染力をなくす処理がされたりして安全性は確保されています。
- 病人やお年寄りなど体の弱った人で肺炎などを起こし、院内感染の原因にもなる真菌が、解体工事現場近くの病室では通常の倍以上飛び交っていることが、国立国際医療センター(東京都)感染制御チームの研究でわかりました。同センターでは2000年10月に敷地内で解体工事が始まった後、入院患者の肺炎が一時増えたため、工事の影響が考えられるとして、感染制御チームが調査に着手。現場に隣接する病棟で、病室の空気中の真菌を調べたところ、窓を閉めた状態では1立方メートル当たり11個でしたが、開けると倍以上の27個に増加していました。工事現場では65個でした。米国では既に、近くで工事がある場合の感染防御の指針があるということです。
- 強い疲労感や発熱などが続く原因不明の「慢性疲労症候群」の発病に、病原微生物リケッチアの一種が関与しているとみられることが、松田重三・帝京大医学部教授らの研究でわかった。リケッチアはコクシエラ・バネッティという種類で、Q熱を引き起こす菌として知られています。松田教授らが、患者138人の血液について、コクシエラ・バネッティのDNAの有無を検査したところ、30人(21.7%)が陽性でした。健康な52人では陽性が5人(9.6%)で、有意な差が認められたということです。コクシエラ・バネッティは牛やヤギなどの家畜にいる菌で、人間に感染するとQ熱を引き起こすことがあり、急性では発熱、頭痛などの症状が出ます。慢性になると、肝炎など合併症のほか、疲労感、脱力感など同症候群に似た症状が出ます。
- 英国の環境・食糧・農村省は2月26日、中部ヨーク州の農場で家畜伝染病、口蹄疫(こうていえき)に感染した疑いのある羊2頭が見つかったと発表しました。英国は昨年2月から口蹄疫の空前の大流行に見舞われ、今年1月に終息宣言を出したばかりです。
- 狂牛病(牛海綿状脳症、BSE)感染の原因とされている肉骨粉をセメントの原料に再利用するための処理作業が3月6日、高知市の太平洋セメント土佐工場で全国で初めてスタートしました。農水省がセメント協会に処理を要請。全国の16工場でも順次処理を始めます。1400〜1500度で肉骨粉を焼成処理すると、感染原因の異常プリオンが破壊され、カルシウムと微量の塩素だけが残り、石灰石などのセメント原料に混入しても品質が落ちないということです。
- 狂牛病問題で、90年に国際獣疫事務局(OIE)が牛などの肉骨粉の輸入政策を見直すよう各国に勧告し、日本の農水省にも届いていたことが、農水省の「BSE問題に関する調査検討委員会」で明らかにされました。同年、英国政府からも「牛などの飼料に肉骨粉を与えることを禁止した」との書簡が農水省あてに届いていたこともわかりました。農水省が行政指導による肉骨粉使用禁止を指示したのは96年のことです。
- 98年6月以前に日本がイタリアから輸入した肉骨粉に狂牛病の病原体・異常プリオンの感染力を失わせる加圧処理が行なわれていなかったことが明らかになりました。日本とイタリアの間では95年3月、異常プリオンの感染性を失わせるため肉骨粉を「136度30分3気圧」という条件で処理することが決まりました。しかし、昨年10月、農水省が職員をイタリアに派遣して調査した結果、この条件を満たす加圧器が98年6月まで肉骨粉製造工場に設置されていなかったことがわかりました。イタリア政府は「98年6月以前の肉骨粉についても3気圧の加圧処理が実施されていた」と説明していましたが、根拠が示されていなかったため、農水省が改めて問い合わせていました。今回の回答は2月9日に届いたということです。
- イタリア・シチリア島のパレルモの病院で2月初め、狂牛病の牛から感染した変異型クロイツフェルト・ヤコブ病の女子学生(23)の患者が出たことがテレビなどで報じられ、人口70万の州都パレルモでは牛肉の売れ行きが大きく落ち込み、食肉解体場も閉鎖されるなどパニックが広がっています。イタリアでの狂牛病を発症した牛は既に60頭近くなっています。
- 香港紙「星島日報」によると、狂牛病との関連が指摘される新変異型クロイツフェルト・ヤコブ病に英国で感染したとみられる香港人の女性(35)が2月20日、香港の病院で死亡しました。この女性は85〜92年まで英国のロンドンやバーミンガムに居住、香港に戻った後もたびたび渡英し、レストランで働いたこともありました。英国滞在の00年10月ごろから、痴呆や歩行障害などの症状が出始め、昨年1月に香港に戻って治療を受けていました。
- 米会計検査院は、狂牛病発生国からの牛肉輸入禁止などの発生予防措置に対する検査が不十分で、米国でも狂牛病が発生する恐れがあるとの報告書を上院に提出しました。狂牛病は英国や日本など世界23カ国で発生していますが、米国では発生が確認されていません。米食品医薬品局(FDA)は発生を予防するため、発生国からの牛肉や内臓などの輸入、動物に由来する飼料の使用を禁止しています。ところが、報告書によると、輸入品の表示ミスや検査員不足が原因で、BSE発生国の牛肉が米国に入る可能性があり、また、動物由来の飼料の禁止措置が徹底されず、長期間にわたり査察を受けていない牧場があって、査察の記録の管理も極めてずさんだということです。報告書は「米国でのBSE発生の可能性は非常に低い」としながらも、「発生した場合、経済的な損失は膨大になる」と指摘し、禁止措置の徹底を求めています。
- ヤコブ病をめぐる裁判で、坂口厚生労働大臣は、すべての患者に対して国が和解金の一部を負担するよう求めた裁判所の和解案を受け入れることを明らかにし、ヤコブ病をめぐる裁判は提訴から5年余りたって全面解決する見通しとなりました。この裁判は、医療用の脳の硬膜の移植を受けて、クロイツフェルト・ヤコブ病になった患者と遺族が、硬膜を作ったドイツのビー・ブラウン社と輸入販売を認めた国に損害賠償を求めているものです。国は硬膜の移植を受けたヤコブ病の患者が世界で初めて報告された昭和62年より前の移植患者については、危険性がわかっていなかったので和解金を負担する理由がないと主張してきました。この点について、坂口厚生労働大臣は「裁判所の和解案を尊重して、弔慰金または見舞い金的性格のものという理解で、国がすべての患者に和解金の一部を負担することにした」と述べ、裁判所の和解案を受け入れることを明らかにしました。
- 薬害ヤコブ病の患者家族の多くが療養中の医療機関で偏見や差別を受け、つらい立場に置かれていたことが、毎日新聞が実施した原告アンケート調査でわかりました。アンケートは大津、東京両地裁の原告患者31人(うち生存4人)の家族を対象に先月から今月にかけ実施、うち26家族の回答を得ました。「医療機関で差別や偏見を感じたことがあるか」との質問には、半数の13家族が「ある」と回答。感染することがないのに「医師がたんを取り除くのを嫌がり、看護婦も患者に恐る恐る触る」「病室の掃除をしてもらえず、風呂にも入れてもらえなかった」「個室に移されて隔離された」「医師から『患者の衣類は焼却しろ』と言われた」など、医療現場の知識が乏しいことが裏付けられました。
- 急速に痴ほうが進み多くは1〜2年以内に死亡するクロイツフェルト・ヤコブ病の患者にマラリア治療薬を投与する、福岡大病院(福岡市)などでの国内初の臨床試験で、6人中4人で症状悪化が止まり呼び掛けに答えるようになるなどの効果が出たことがわかりました。臨床試験は昨年11月から、福岡大病院に入院中の4人と、栃木県と奈良県の各1人の計6人に順次、実施。マラリア治療薬キナクリンを1日3回、100ミリグラムずつ経口投与しました。発病間もないか長期でも進行の遅い患者4人(福岡3人、栃木1人)は、投与開始数日後から効果が表れました。それまでは呼び掛けにも無反応だったのに「おはようございます」とはっきり返事をしたり、寝たきりだったのが座れるようになったりしたということです。しかし、このうち2人では、効果が1〜2カ月続いた後、次第に低下しました。キナクリンは、ヤコブ病を引き起こす感染性タンパク質、異常型プリオンの増殖を抑制することが培養細胞で確認されていますが、なぜ効果を持続できないか、メカニズムの解明が課題です。
- 雪印乳業(本社・東京)が1月まで、品質保持期限の切れた業務用冷凍バターを、先送りした期限を書いた箱に詰め替えたうえで再利用していたことがわかりました。北海道の調査では、昨年3月からだけで約11万5000箱(2300トン)が詰め替えられ、うち約3万8000箱(760トン)は既に加工乳などに製品化されていました。同社の竹之内英毅常務は、北海道支社で行った記者会見で、91年から期限切れバターを一部、社内で再利用していたことを認めました。この際は、詰め替えはせず、そのまま加工乳などにしていたということです。
- 全国農業協同組合連合会(全農)系の鶏肉加工会社「鹿児島くみあいチキンフーズ」(鹿児島市)が、コープネット事業連合(さいたま市)に納入した鹿児島県産の産直若鶏の中に、タイや中国産鶏肉を少なくとも7トン混ぜていたことが、明らかになりました。偽装は狂牛病騒ぎで、鶏肉の需要が急増し、欠品対策として全農の子会社「全農チキンフーズ」(埼玉県戸田市)の指示で行われたということです。問題の商品は、東京、千葉、埼玉など首都圏6生協が加盟する同連合と全農が共同で企画した「無薬飼料飼育産直若鶏」の手羽肉で、抗生物質を使わず、非遺伝子組み換えの飼料で飼育するというのが売り物でした。
▲ 目次にもどる
金属・化学物質
- 人体に有害な鉛対策として厚生労働省は、鉛の水道水質基準を世界保健機関(WHO)のガイドライン(指針値)と同じ1リットル当たり0.01ミリグラム以下とし、現行(0.05ミリグラム以下)の5倍に規制を強化する方針を決めました。水道法関連の省令を近く改正し、2003年4月に施行する予定です。厚労省は鉛製から塩化ビニール製やステンレス製などへ給水管の交換を呼び掛けますが、費用面の問題から、施行までの取り換え完了は困難。同省は水道水の酸性を抑える「pH調整」など、鉛の溶出を防ぐ緊急措置を取るよう水道事業者への指導を徹底します。WHOのガイドラインは、鉛の蓄積性を踏まえた上で、大人が毎日2リットル、乳児が0.75リットルの水を飲んでも将来にわたって健康への影響がない値として設定されています。道路の下に埋設されている配水管から水道水を住宅内に引き込む給水管に鉛を使っているのは、1999年の段階で全世帯の5分の1に当たる約852万世帯。鉛は加工しやすいため、80年代後半まで一般的に使われていました。鉛製給水管をすべて取り換えるには1兆3000億円掛かるとされ、全世帯で交換が完了するめどは立っていないのが実情です。
- 世界保健機関(WHO)がバンコクで開いていた環境汚染と幼児の健康に関する国際会議は「アジアの各政府に対し、自動車に使うガソリンから鉛の除去を求める」などの勧告をまとめました。同会議は、鉛は脳に障害を与えるため「子供の健康へのダメージだけではなく、アジアの将来の知力や経済的能力に多大な悪影響を与える」と結論付けました。背景としてアジアの工業化と、有毒廃棄物に対するずさんな対応を挙げています。アジア各国では有鉛ガソリンが広く使われていますが、日本では1986年以降、使われていません。
- 環境省は、日本人が1日に吸収しているダイオキシンの量は体重1キロ当たり2.3ピコグラムで、基準値の4ピコグラム以下との推計結果を発表しました。食事からの摂取が9割を占める。1999年度の自治体などの調査に基づく推計値で、国が実施した98年度調査による推計値と同じ。しかし、同省環境リスク評価室によると、計算上、2%の人が基準値を超えることになるということです。世界保健機関(WHO)では1ピコグラム以下を目標としています。また、2000年度に実施した野生動物の体内へのダイオキシン蓄積状況調査から、アカネズミでは量が2年前に比べ約30分の1に減っていることがわかりました。アカネズミの寿命は約2年と短いことから、評価室では「環境全体のダイオキシン濃度が減っていることが反映しているのではないか」としています。だが、寿命がより長く魚を食べるトビ、カワウ、スナメリなどでは比較的高濃度に蓄積しており、過去2年の調査結果と同様の傾向でした。
- ダイオキシンを分解できるセラミックスの繊維を、宇部興産宇部研究所(山口県宇部市)の石川敏弘・機能材第一研究部長の研究グループが開発しました。強い酸化力がある二酸化チタン(チタニア)の微粒子を表面に持つ構造。チタニアは紫外線を受けると、ダイオキシンを水と二酸化炭素に分解します。2.37ピコグラムのダイオキシンを含む1リットルの水に、この繊維2グラムを入れて紫外線を10時間あてると、ダイオキシンの9割以上が分解されました。シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドや、肺炎の原因となり院内感染がよく問題化するレジオネラ菌などの分解にも使えるということで、同社は空気清浄機や水の浄化装置への利用を計画しています。
- 火力発電所などから出る産業廃棄物の石炭灰と、火山灰から抽出した粘土物質「アロフェン」を混ぜることで、生物の生殖に悪影響を及ぼす環境ホルモンなどの有害物質を常温、低コストで分解できることが、信州大と地元企業の共同研究でわかりました。信州大工学部(長野市)の藤井恒男教授(光化学)らの産学協同研究グループが、2物質について実験に成功しました。実験で、塩化ビニールを加工する際に使う環境ホルモンの「フタル酸ジエチル」にアロフェンを混ぜたところ、フタル酸ジエチルの分子構造の骨格部分から伸びた枝の部分が根元から切断されました。アロフェンと化学構造が似ている石炭灰を混合すると、分解力がさらに増すこともわかったということです。環境ホルモンと分子構造が似ている発がん性物質「トリクロロエチレン」も、同じ方法で分解に成功しました。
- トリクロロエチレンや鉛、ヒ素などの有害物質による工場跡地などの土壌汚染で、環境基準を超えた事例が2000年度は134件に上ることが、環境省の調査でわかりました。前年度の129件を上回り過去最高。同省土壌環境課は「土壌汚染に対する国民の意識が高まり、調査件数自体が増えているため」と説明しています。
- シックハウス症候群を防ごうと、住宅関連9団体でつくる住宅生産団体連合会(奥井功会長)は、住宅建材に含まれるホルムアルデヒドなどの化学物質の影響による健康被害を防止するための小冊子を発行しました。小冊子は、住宅の設計段階から防止策をアドバイス。さらに、建てた後には(1)ホルムアルデヒドがあまり出ない材料でできた家具やカーテンを選ぶ(2)入居から数カ月はこまめに窓を開けるなど通風、換気を十分にすることで室内の化学物質を減らす、などとアドバイスしています。小冊子は1部300円(送料別)で、注文は20冊以上から受け付けます。問い合わせは同連合会、電話03-3592-6441。
- 滋賀県の国松善次知事は、水質悪化を防ぐため、2ストロークエンジンを搭載している水上バイクを琵琶湖で禁止する条例案を、6月をめどにまとめる方針を表明しました。来年夏のシーズンからの適用を目指します。同エンジンの水上バイクの排ガスには、炭化水素や窒素酸化物など有害物質が多く含まれているためです。メーカーは既に有害物質を減らした改良型2ストローク搭載機を販売、排ガスがさらに少ない4ストロークの水上バイクも4月以降発売する予定で、これらは禁止対象に盛り込まない方針です。
▲ 目次にもどる
薬品・食品
- 「マジックマッシュルーム」という名前でインターネットなどを通して販売されている「きのこ」の一種に幻覚作用があるとして、厚生労働省はこのきのこを法律に基づいて麻薬原料に指定し、使用や所持、栽培などを禁止することになりました。マジックマッシュルームは、幻覚作用のある「サイロシビン」と「サイロシン」という麻薬成分を含むきのこで、世界各地に自生し、インターネットや繁華街の店舗で販売され簡単に手に入るため、日本中毒情報センターによりますと、若者が吸飲して、中毒や幻覚作用を起こした事例がおととしには32件報告されています。このため厚生労働省は、法規制の対象に加えることを決めたもので、サイロシビンとサイロシンを含む、きのこそのものを麻薬原料に指定し、輸入や所持、栽培などを禁止することになりました。
- 国際オリンピック委員会(IOC)は、ソルトレークシティー冬季五輪のノルディックスキー距離男子50キロクラシカル優勝のヨハン・ミューレック(スペイン)、同女子30キロクラシカル優勝のラリーサ・ラズティナ(ロシア)、同8位のオルガ・ダニロワ(ロシア)がドーピング(禁止薬物使用)検査で陽性反応を示したため、失格、追放処分を科したと発表しました。3選手から検出されたのは、禁止薬物のエリスロポエチン(EPO)に類似したダーベポエチンで、赤血球増加ホルモンの一種です。
- ソルトレークシティー冬季五輪に出場したスキー距離のオーストリア・チームの宿舎から、輸血用の器具が発見されたことがわかりました。国際オリンピック委員会(IOC)は輸血をドーピング規定で禁止しています。
- 冬季パラリンピックで初めて、ドーピングによる失格者が出ました。ノルディックスキー男子のエールスナー(ドイツ)が、筋肉増強剤の一種「メテノロン」の陽性反応を示しました。00年のシドニー夏季パラリンピックでは11人が失格になり、パワーリフティング選手の金メダルがはく奪されています。
- 日本メナード化粧品(名古屋市)は、排ガスやたばこの煙に含まれる成分が紫外線A波に当たってシミの原因となる炎症を引き起こすことを突き止めたと発表しました。紫外線の中のより短い波長のB波が肌に炎症を起こしてシミになることは知られていました。メナードによると、たばこの煙などに含まれるベンツピレンと呼ばれる有害物質を皮膚に塗り、紫外線A波を照射したところ炎症が起きました。ところがA波を当てなかった場合炎症は見られませんでした。この結果、紫外線A波がベンツピレンに当たることで強い刺激物質に変わって肌に炎症を引き起こし、それを繰り返すことでシミの原因となるメラニンが過剰につくられる、という結論に達しました。
- 香港大学は、非喫煙者の母親が妊娠中に頻繁に受動喫煙にさらされた場合、子供が生後18カ月以内にぜんそくなど呼吸器系の疾患で病院に行く割合が、受動喫煙にさらされない場合に比べて26%高くなるとの調査結果を発表しました。同大は1997年に非喫煙者の母親から生まれた約8300人の乳児を調査。母親の約14%が毎日、約50%が時々受動喫煙にさらされており、受動喫煙者の子供は入院する割合も18%高くなっていました。また、家庭に喫煙者が1人いると乳児が入院する可能性は7%、2人以上いると30%それぞれ高くなるということです。同大は「母親が受動喫煙にさらされると胎児の肺機能に影響し、アレルギーになる可能性が2〜3倍高くなるほか、体重が平均で200グラム軽くなる」と警告しています。
- 低タール、低ニコチンを売り物にしたたばこでも、銘柄によってタールは表示の約7倍、ニコチンも約5倍の量を吸い込む可能性が大きいことが、厚生労働省の分析でわかりました。同省は売り上げが多い中から7銘柄を選び、カナダの検査機関に2000万円で分析を委託。煙に含まれるタール、ニコチンなどの発がん物質を含む約30項目を測りました。たばこの成分は、1本を消費したときに吸い込むと想定される量で示されます。分析の前提とした吸い方は(1)65年当時の吸い方に基づく国際基準で、メーカーが現行の表示に採用しているもの〔フィルター側面の通気孔を開放し1分間隔で1回に2秒かけて35ミリリットルを吸引〕(2)今の現実の吸い方に近くて米国やカナダ保健省で採用されているもの〔通気孔を半分閉じて30秒間隔で1回に2秒、45ミリリットル吸引〕。表示と最もかけ離れていたのは「タール1ミリグラム、ニコチン0.1ミリグラム」という銘柄。(2)の吸い方では、タールは表示の6.7倍、ニコチンは4.8倍でした。差が最小の銘柄でも、いずれも2.2倍でした。ベンゾピレンやベンゼンといった発がん物質も「軽い」銘柄の方が「重い」銘柄より多い場合がありました。
- 英国最大、世界第2のたばこメーカー経営者が「自分の子どもに、喫煙しないよう説き続けてきた」と英紙に明言したことが1面トップ記事になりました。ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(BAT)のマーティン・ブロートン会長は「息子と娘に、たばこは健康に悪い、吸わない方がいい、といってきた」と語りました。二人とも非喫煙者だが、「もし吸っているのを見つけたら、厳しく警告しただろう」。病気への恐れから、自身も吸わない事実を認めました。反たばこ派団体の代表は「子どもの健康を案じる模範的な父親が、他人の子にはますますたばこを買わせている」と皮肉りました。
▲ 目次にもどる
電磁場・放射線
- スウェーデン誌、Vibilagareは、自動車14車種の電磁場に関する調査の結果、ボルボ製の3車種で計測された電磁場の結束密度が、最高で安全基準値(0.2マイクロテスラ=2ミリガウス)の80倍に達していた、と述べました。この調査によると、ボルボの「V70」、「S60」、「S80」の3車種を運転した場合、最高で12〜18マイクロテスラの結束密度を持つ電磁場にさらされました。電磁場が特に強いのは運転手の左足付近でした。最も電磁場が弱かったのは同じボルボのV40でした。を超える場合は、人体に害が及ぶ可能性があるという。調査はフォード、フォルクスワーゲン、BMW、メルセデス・ベンツ、サーブ、ルノー、トヨタの14車種を対象に実施されました。
- 地上核実験の死の灰で米国内だけで1万5000人以上ががんで死亡したと、米紙USAトゥデーが伝えました。米疾病対策センター(CDC)と国立がん研究所(NCI)による未公開の研究結果としています。研究によると、従来知られていたよりもはるかに大量の死の灰が、旧ソ連や米英の核実験場から届いていました。このため、米ソの核実験が本格化した51年以降、米国に住んだ人は全員が死の灰の影響を受け、がんによる死者が少なくとも1万5000人増えました。さらに2万人以上が死には至らなかったものの、がんにかかったと分析しています。増えたがん死のおよそ4分の3は死の灰による外部被ばくで、残りは死の灰を吸い込んだり、汚染されたものを飲食したりして起きる内部被ばくです。
- 原子力施設の事故などの際に放出された放射性物質が人の甲状せんに蓄積されるのを防ぐ「ヨウ素剤」について、原子力安全委員会の専門部会は副作用のおそれがあるとして、服用する量をこれまでより大幅に減らした新しい基準案をまとめました。原子力安全委員会の専門部会はWHO=世界保健機関のガイドラインを参考にヨウ素剤の服用基準を見直しました。それによりますとまず、服用回数については、これまで1日1回、状況に応じて3日から7日連続して服用するとしていたものを、原則として1回に限るとしています。また、1回当たりの服用量も、13歳以上はこれまでと同じ100ミリグラムとしていますが、12歳以下については半分から4分の1に減らし、3歳から12歳までは50ミリグラム、1か月から2歳までは25ミリグラム、1か月未満は12.5ミリグラムとしています。
- 放射線を浴びる前にビールを飲んでおくと、被ばくによる障害を予防できる可能性のあることが、放射線医学総合研究所(千葉市)の実験でわかりました。同研究所の安藤興一グループリーダー(放射線生物学)らは、同研究グループの千葉大大学院生、物部真奈美さんが、空腹状態でビール0.7リットル(大瓶約1本)を飲んだ後に、血液を採取。この血液にエックス線や重粒子線(炭素イオン)を照射し、リンパ球の染色体に生じる異常を調べました。その結果、飲酒後の血液は、染色体の異常が、飲酒前の血液の約3分の2に減少していました。放射線を浴びると、体内に「フリーラジカル」という反応性の高い分子ができ、遺伝子を傷つけて、がんなどの原因になります。アルコールは、ラジカル分子を消す働きをもつことが知られていますが、今回は、飲酒から4時間以上後のアルコール濃度が下がった血液でも効果が続きました。ラジカル分子を発生させずに遺伝子を直接壊すことが多い重粒子線に対しても、飲酒後の血液は損傷が少なかったということです。
- 人体にさまざまな影響を及ぼす紫外線の研究で、京都大原子炉実験所、防衛医大、旭テクノグラスの共同研究グループは、通常「左型」だけでできている皮膚のたんぱく質のアミノ酸が、紫外線を浴びて、異常な「右型」のアミノ酸に変化している可能性を明らかにしました。たんぱく質を構成するアミノ酸には、分子構造は同じですが、実像と鏡に映した像との関係にある「右型」「左型」の2種類があります。地球上の生物はすべて左型のアミノ酸から構成されますが、高齢になると、目のレンズの水晶体などに右型アミノ酸が少しずつ増えてくることがわかっています。研究グループは、右型アミノ酸を含むたんぱく質にだけ反応する抗体を作りました。その抗体を使って、9〜11歳の子供と、60〜80歳の老人数人ずつの顔の皮膚組織を調べたところ、右型アミノ酸は老人の顔の皮膚の約3割の部分に見られましたが、子供にはありませんでした。しかし、老人の腹部や胸部の皮膚には、右型アミノ酸は存在しないこともわかり、右型アミノ酸が、日光の影響を受けてできたことが示唆されました。
- 「モントリオール議定書」によって、製造・輸入が原則禁止されているフロンガス(CFC12)の密輸事件が、昨年夏以降、相次いでいます。未遂、既遂合わせて密輸CFC12は計50万缶(15万キロ・グラム)に上ります。「モントリオール議定書」は、地上の人間を含む生物を有害な紫外線から守る大気中のオゾン層の破壊を防ぐため、1987年に採択されました。オゾン層を破壊するCFC12などのフロンガスの生産を先進国には95年末までに全廃することを義務づけたもので、日本政府も88年に同議定書を批准しました。密輸の続発は、昨年ごろから旧式エアコンがガス交換の時期を迎えているうえ、国内で禁止措置が取られた95年末より前に国内で製造されたCFC12の在庫が少なくなってきたためとみられますが、日本の自動車保有総数約7000万台のうち、約3割にあたる約2000万台が旧式のカーエアコンを搭載しているとされます。CFC12を使わない場合、ユーザーは、「代替フロン」を使う新しいカーエアコンに転換することになりますが、数万円の費用がかかるため進んでいません。一方、同議定書では、途上国の生産全廃は2009年末までとされており、中国など途上国のメーカーが密輸フロンの供給源となっています。密輸フロンの問題に取り組むロンドンのNGO「環境捜査局(EIA)」の研究担当者、エズラ・クラーク氏は「販売、使用の禁止措置が必要だ」と指摘しています。
▲ 目次にもどる
環境
- ヒノキに含まれる揮発成分を使って、ディーゼル車の排ガスに含まれる有害物質ディーゼル排気微粒子(DEP)を除去し、無害化する浄化装置を、産学協同の研究チームが開発しました。開発したのは高知工科大学の河野雅弘教授と環境関連ベンチャー企業、ジュオンメディカルシステム社(東京)。同社は、ヒノキの揮発成分を封入したフィルターを開発しました。河野教授らは、これを使った空気清浄機が空気中のホルムアルデヒドや、たばこの煙などを極めて効率よく取り除くことに着目。これをDEP除去に応用しました。ヒノキフィルターはDEPを80〜90%除去するほか、DEPに含まれ、ぜんそくや肺がんの原因とされる活性酸素などの毒性物質も、約10%にまで減少させることに成功しました。ディーゼル排ガスの浄化装置としては、セラミックフィルターで集めた粒子状物質を燃やす装置などがあるが、目詰まりや窒素酸化物の増加などの課題に加え、価格も80万〜200万円とかなり高額。ヒノキフィルター装置は、12万〜18万円程度ででき、4月にも実用化される予定です。
- アジア大陸で発生した大気汚染物質の一酸化炭素が、西からの季節風に乗って日本上空に運ばれてくる様子を、宇宙開発事業団の研究チームが航空機を使った大気成分の観測調査でとらえ発表しました。工場などから排出される二酸化硫黄などの微粒子が日本近くに流れてくる現象は、衛星観測データなどから知られていましたが、これだけ広い範囲で直接、大気成分を調べたのは初めて。今年1月に専用ジェット機を使い、新潟県沖から小笠原諸島、沖縄までの日本近海で上空2キロまでの大気中の一酸化炭素や微粒子などを成分分析。その結果、東シナ海や日本海沖などの海上で、汚染のない海域に比べ3倍以上の濃度の一酸化炭素が検出されました。同事業団は「海上には排出源がないため、西からの季節風に乗って運ばれてきたのは間違いない」とみています。
- コンピューター関連のハイテクごみが米国から中国などに大量に輸出され、環境汚染を招いているとの調査結果を米国の環境保護団体バーゼル・アクション・ネットワーク(BAN)などが発表しました。調査によると、米国で発生するパソコンやディスプレー、プリンターなどのハイテクごみの50〜80%が、インドや中国、パキスタンなどにリサイクル目的として輸出されています。中国広東省のある町では、ハイテクごみを燃やして金や銅などを集める作業に子供を含めた10万人が従事。環境汚染のため1995年から地下水を飲むことができなくなっていました。周辺の河川からもこの作業が原因とみられる高濃度の重金属などが検出されました。米国は、鉛などの有害物質を含む廃棄物を先進国から途上国に輸出することを禁じたバーゼル条約の規制を批准しておらず、リサイクル目的での輸出は合法。BANのリチャード・ガティレッツさんは「米国政府は一刻も早く条約の禁止措置を批准し、欧州諸国のように企業にリサイクルの義務を課す必要がある」と話しています。
- 米海洋漁業局(NMFS)は、海に生きる哺乳類保護を徹底するために、人間と海の哺乳類との行き過ぎた接触行為を法律で規制する方針を決めました。NMFSが規制対象とするのは、ボートで近づいて鯨に触ったり、イルカと一緒に泳いだりするなどの行為。カヤックやカヌーで静かに近づいて、すぐ近くから写真を撮ったりすることや、陸上にいるオットセイやアシカに触ったり、一緒に写真を撮ることなども含まれ、こうした行為を海生ほ乳類保護法の「動物に危害を加えたり、いやがらせをする行為」として厳しく規制する方針ということです。鯨やイルカとボートとの接触事故や、人間の影響で海のほ乳類の親が子育てを放棄した例などが増えており、また、人間や人間が飼育する動物と共通した病気に海のほ乳類が感染する危険も出てきた、というのが規制強化の理由です。
- ペットとして国内に持ち込まれ野生化したと見られる北米原産のアライグマが全国各地に出没し、農作物などに被害を与える例が急増していることが、北海道大の池田透助教授の調査でわかりました。1960年度以前は全く報告例がなかったのに、90年度以降はそれが39都道府県に広がったとしています。都市近郊など人の生活環境を好むとされ、北海道の牧場や神奈川県鎌倉市の住宅地で大量繁殖が確認されています。
▲ 目次にもどる
生活・ストレス
- 飛行機の狭い座席に長時間座ったままでいると、血液が固まって血栓ができ、脳や心臓などに障害を起こすことがありますが、こうした「エコノミークラス症候群」の予防にポカリスエットが役立つ可能性が出てきました。飛行機での旅行中にポカリスエットを飲むと、水を飲んだ時よりも、足の血液の粘度が上昇しにくいことがわかったためです。ポカリスエットの発売元である大塚製薬と日本航空の研究グループは、成田から米国Washington州まで飛ばしたチャーター便の中で、40人の健康な男性(平均年齢23.4歳)をくじ引きで2グループに分け、一方にはミネラルウォーター、もう一方には糖電解質飲料(ポカリスエット)を、同じ量だけ同じタイミングで飲んでもらいました。フライト終了後、糖電解質飲料を飲んだ人の方が水分バランスが良好なことが判明。腕と足から血液を採り、粘度を調べると、足の血液では糖電解質飲料を飲んだ人の方が粘度の上昇度が少ないことがわかりました。体のむくみも、糖電解質飲料を飲んだ人の方が少なかったということです。ちなみに、実験では5回に分けて水分を摂り、飲んだ水分量は合計で1320mlでした。
- 長期間にわたり自宅に閉じこもり社会参加しない「引きこもり」からの脱出を支援するため、岡山県は、引きこもり経験者を相談員(サポーター)として育成、活用する「引きこもり脱出支援事業」を4月から始めることを決めました。当事者の気持ちを理解しやすい経験者によるケアを、自治体が積極的に進める試みです。精神科医による専門的な研修を受けた経験者やその家族らがサポーターとして県内の保健所に待機。引きこもりの家族を抱える人からの電話相談などに応じます。希望があれば家庭訪問も実施します。
- 英軍の元兵士15人が、戦場で受けた心の傷を放置されたため、後遺症に苦しめられたとして、国防省を相手取り損害賠償を求める訴えをロンドンの高等法院に起こしました。この元兵士たちは90年代前半ボスニア紛争や湾岸戦争に従軍。今後2000人近くが原告に加わる見通しです。原告側はこの日の弁論で、過酷な経験の後、幻覚や悪夢に悩まされ、アルコール中毒になったり、犯罪を犯した者もいると主張。国防省側はトラウマに苦しむ元兵士がいる事実を認めつつも、「補償する責任はない」と反論しました。
- 昨年9月の米同時多発テロから半年。冷戦終結後の米国の一極支配の傾向は同時テロを境に一気に強まりました。「テロとの戦争」の戦線を拡大する米国は、他方では「独断的」とされる外交姿勢の見直しも迫られています。●米スタンフォード大のデービッド・シュピーゲル教授(精神医学)は、被害者や関係者7000人から集めた声を整理中です。「人生の中での優先順位を考え直している人が多い。カネもうけより家族や友人を大切だと考えたり、地域社会への貢献を重視する人が増えている」と分析しています。●ニューヨーク市によると、世界貿易センタービルでの死者・行方不明者は3月8日現在で2830人。テロ発生直後には5000人を超えると言われ、11月時点で3646人という数字が発表されました。しかしその後、無事が確認されたり、虚偽の申告が発覚したり、数え間違いが分かるなどして総数が減少しました。遺体が確認されたのは753人にとどまっています。
- 世界貿易センタービルが崩壊したニューヨークでは、現場付近で働く消防士や周辺の住民の間で、崩壊の際に飛び散った粉じんによる健康への影響に対する不安が広がっています。ニューヨークでは、世界貿易センターの崩壊でマンハッタンの南部一帯が大量の粉じんに覆われました。このなかにはアスベストやガラス繊維、それに鉛、水銀などの重金属といった有害物質が含まれていたことが明らかになっています。事件直後から現場で捜索活動にあたってきた消防士の多くが息苦しさやぜんそく、さらには神経障害などの症状を訴えています。消防士からの相談を受けている弁護士によりますと、これまでにおよそ700人が健康障害を理由に休職を命じられたということです。また、周辺に住む住民のなかにも、家の中に入り込んだ有害物質が完全に除去されず、これを吸い込んだために健康を害したという不安を訴えている人が少なくありません。
- 米首都ワシントン近郊にあるメリーランド州の郵便集配施設で、炭疽菌対策として放射線を照射した郵便を扱った職員の多くが吐き気などの体調不良を訴えています。地元郵便労組の話では、同施設で働く750人のうち、少なくとも87人に強い頭痛、鼻血、視覚や呼吸異常の症状が出ているということです。米国では1月10日、放射線照射の郵便を開封した米商務省の職員11人が吐き気や呼吸困難を訴え、2人が病院に収容されました。
- アフガニスタン西部のヘラート州やファラー州では、100キロの小麦粉と引き換えに10歳の女の子が花嫁として身売りされています。最近現地を訪れた国際赤十字の視察団は長年の戦争や過去3年の干ばつによる飢饉の深刻さを訴えました。それによると、視察団は村々で木の葉や地面から掘り出した根を食べている子供を目撃。干ばつで農業はできず、家畜も売り尽くされていました。調査の結果、視察した12の村の住民約1万人のうち510人が孤児で、700人の老人が外国へ難民として逃れた家族からの送金などに頼る生活をしていました。北部マザリシャリフでも貧困は深刻で、家族が1カ月生き延びるために子供が生まれる前から売買契約を交わすケースもあるということです。
- イスラム教の「殉教」観念の影響が強いと言われてきたパレスチナ人の対イスラエル「自爆テロ」から宗教色が薄れ始めています。1月下旬から再燃した自爆テロはすべてイスラム過激派ではなく、世俗派武装組織が犯行声明を出しました。自爆テロは、「聖戦(ジハード)による死は神に祝福される」とのイスラム教の教義が生み出していると理解されてきました。だが、精神病医学者で元国連人権高等弁務官事務所ガザ代表のリヤド・サラジ氏は、「パレスチナ人を自爆に駆り立てるのは、もはや宗教的動機ではなく絶望だ」と分析しています。
- 米紙ワシントン・ポストは、ブッシュ政権が国際テロ組織「アルカイダ」による核攻撃を警戒し、昨年11月から数百の放射線探知装置を国境やワシントン周辺の施設に配備していると報じました。また同装置が核の米国持ち込みを探知した場合に備えて米軍特殊部隊「デルタフォース」を待機させ、核所持者を発見した場合は殺害を認めています。
- 西アフリカのギニアなど3か国で難民の支援活動に当たっている国連の機関や民間の援助団体の職員が、援助物資と引き換えに、難民の少女らに性的な虐待を加えていた疑いが強まり、国連は本格的な調査に乗り出しました。これは、UNHCR=国連難民高等弁務官事務所とイギリスのNGOが現地で行った聞き取り調査で浮上したもので、内戦などの結果、多くの難民が出ている西アフリカのギニアとリベリア、それにシエラレオネの3か国の難民キャンプで、未成年の少女たちが食糧や薬品などの援助物資と引き換えに、国連機関や民間援助団体の一部の職員に性的行為を強要されたと証言しています。こうした行為を行っていたとされる職員の多くは、国連や援助団体が現地で採用したスタッフで、なかには国連の平和維持活動で外国から派遣されてきた要員も含まれていたということで、被害にあった少女たちに名指しされた職員の数は、40の機関や組織のおよそ70人に上るとしています。
- 2月25日午前9時10分ごろ、東京都文京区千駄木一丁目の日本医大病院1階の集中治療室(ICU)の窓から、入院中の指定暴力団住吉会系の石塚隆組長(54)=豊島区要町=に向け、男が短銃4発を発射して逃走しました。石塚組長は頭などを撃たれ間もなく死亡しました。
▲ 目次にもどる
有益物質
一般に有益とされる事項に分類されるものの情報です。
好ましくない副作用などの情報も含みます。
薬品・食品・水
- 慢性腎不全に伴う貧血治療のために、遺伝子組み換え型のエリスロポエチン(rHuEPO)を投与していた患者の中から、再生不良性貧血の一つである「赤芽球癆」が、過去3年間にフランスと英国で13人に発症していたことが報告されました。赤芽球癆は、赤血球の変形を特徴とする難治性の貧血。フランスDieu病院血液・核医学部門のNicole
Casadevall氏らが報告した13人中12人がエポエチンα(わが国での商品名:エスポー)、一人がエポエチンβ(同:エポジン)を投与されていました。赤芽球癆の診断は、12人が骨髄中の赤芽球の欠如、一人が網状赤血球の欠如という所見に基づいています。赤芽球癆で通常大きく上昇する血清EPO濃度が、検出不能(10人)か正常レベル(3人)であり、血清中にEPOと結合する中和抗体が存在し、EPOを測定できないためと推察されました。Casadevall氏らは、放射性元素でラベルしたrHuEPOと、患者および対照の健常者の血清とを共培養し、rHuEPOとの免疫複合体を分離、定量した。その結果、健常者の血清や、赤芽球癆発症前の患者血清(4人)では生じなかったrHuEPOの免疫複合体が、赤芽球癆発症後の患者血清では全例で生じていることが判明しました。
- 遺伝子組み換え型のエリスロポエチン(rHuEPO)を投与中の患者から、赤芽球癆が13例発生したとの報告に関し、米国Brighamand
Women's病院のH. Franklin Bunn氏は、発症者がここ3年に集中しており、欧州のみで発生がみられる点から、欧州での製法変更が関与している恐れがあるという論説を報告しました。rHuEPOは15年前から臨床現場で使われており、既に300万人の患者に投与されています。それにもかかわらず、赤芽球癆が最近になって、しかも欧州のみで報告されている点にBunn氏は着目。「欧州でのrHuEPOの抗原性が、分子全体や糖鎖の構造を変えた製法の変更によって出現したのではないか」との疑念を提示しました。さらにBunn氏は、rHuEPOを架橋して血中半減期を延長した、新型製剤のダルベポエチンα(欧米での商品名:Aranesp、わが国でも開発中)(※冬季オリンピックでドーピングが発覚)では、「構造的には従来のrHuEPOより、さらに内因性のEPOとの違いが大きくなっている」と指摘。今後、同薬が同様の交差反応を起こす抗体を産生するかどうかを見極める必要があると強調しています。
- 喘息に罹患している1〜3歳の幼児を対象としたプラセボ対照二重盲検試験で、吸入ステロイドにわずかながら下肢の成長を抑制する作用があることがわかりました。デンマークCopenhagen大学病院小児科のJacob
Anhoj氏らは、喘息にかかっている1〜3歳の幼児40人(うち女児20人、平均年齢2.4歳)を対象とした臨床試験を行いました。成長への影響は、下肢の長さを100分の1センチまで測れるネモメーターという装置を使って3週間隔で測定し、1日当たりの成長速度を指標に評価しました。その結果、プラセボを服用した期間の下肢の成長速度は、1日当たり85μm。ところが、ブデソニド(1日量400mg)服用中は45μm、プロピオン酸フルチカゾン(1日量400mg)服用中の場合は34μmとなり、いずれもプラセボ服用中より有意に成長抑制が起こっていることがわかりました。研究グループは、下肢の成長速度にみられた差は、副腎機能の抑制作用を反映していると指摘。乳幼児に吸入ステロイドを安全に使用するためにも、喘息の治療効果に加え、副腎機能などを評価する臨床試験が必要だと示唆しています。
- 軽症の喘息患者を対象としたプラセボ対照二重盲検試験で、吸入ステロイドによる治療効果が、喫煙者には現れないことが明らかになりました。英国Western病院呼吸器部門のG.
W. Chalmers氏らは、気管支拡張薬(β刺激薬)の使用歴はあるが、これまで吸入ステロイド治療を受けたことがない喘息患者47人を対象に、試験の前半と後半で実薬群とプラセボ群とを入れ替えるクロスオーバー試験を実施。非喫煙者では喘息の病態を反映する指標がステロイド吸入時に有意に改善しました。ところが喫煙者では、プラセボを吸入した時とステロイドを吸入した時とで、起床時のピークフロー値やFEV1、喀痰中の好酸球比率、気道過敏性などの検査結果に違いが現れませんでした。たとえ軽症でも、喘息患者には十分な禁煙指導を行うべきと提言しました。
- 薬局で売っている咳止め薬に、「咳が止まる」という効果を示した研究結果がほとんどないことが、英国で行われた調査で明らかになりました。英国の国民保健事業(NHS、日本の国民健康保険に相当)で、「市販の薬で治せる病気は、市販薬を買うように勧める」というのも、医療費削減策の一つです。英国では、風邪(上気道感染)に伴う咳については、医師に対して、「市販薬を使いなさい」と患者に勧めることが推奨されています。英国Bristol大学プライマリ・ケア部門のKnut
Schroeder氏らは、こうした政策が「医学的に妥当」かどうかを調べるため、市販の咳止めについて調べた研究論文を検索。病院で処方される医療薬と同じように、厳密な方法で有効性が調べられている論文を探しました。ところが、見つかった328本の論文のうち、医療薬と同じくらい厳密な研究が行われていたのはわずか15本。その15本も、同じ咳止め薬について効果が「ある」「ない」と結果がばらばらだったり、思い込みで結果を見誤らないために使うプラセボ(偽薬)と効果が変わらなかったりといったものでした。以上からSchroeder氏らは、「市販の咳止め薬には、“効く”根拠が希薄」と結論。「効くかどうかわからない薬を買うのはお金のムダでは」と、手厳しい評価を下しています。
- ビスフォスフォネート製剤(ビス製剤)のゾレドロン酸を静脈内に1回投与するだけで、骨密度の増加や骨代謝マーカーの改善作用が、少なくとも1年間続くことがわかりました。ニュージーランドAuckland大学のIan
R. Reid氏らは、骨量が低下した閉経後女性351人を対象とした第2相試験を行いました。骨量が低下した閉経後女性に高用量のゾレドロン酸を1回静脈内投与すれば、低用量の同薬を3カ月に1回投与した場合と同じ効果が少なくとも1年間続くということが判明しました。腰椎で年に約5%という骨量増加が見られました。
- 変形性膝関節症(OA)の保存療法として、膝関節内にヒアルロン酸を注入する治療の有効性を調べた無作為化試験の結果が発表されました。カナダWestern
Ontario大学Lawson究所のRobert John Petrella氏らは、120人のOA患者を調査し、安静時の痛みに関して「ヒアルロン酸はNSAIDと同等」、運動に伴う痛みや運動機能については「ヒアルロン酸はプラセボ単独やNSAID単独よりも有用」と結論付けました。
- ボツリヌス菌による食中毒の抗毒素など、国が買い上げて備蓄している3種類の薬品が来年以降、国内で確保できなくなる恐れがあることがわかりました。これらの薬の国内唯一の製造元で、今年9月に閉鎖される千葉県の公営企業「千葉県血清研究所」(同県市川市)の業務を引き継ぐメーカーがいまだに見つからないためです。3つの薬品は、ボツリヌス菌中毒の治療に使う「乾燥ボツリヌスウマ抗毒素」と、筋肉の壊死を起こすガス壊疽を治療する「ガスえそウマ抗毒素」、ジフテリア治療用の「乾燥ジフテリアウマ抗毒素」。年間の患者数は、数人から十数人程度と少ないのですが、緊急時の備えとして欠かせないため、国が毎年予算を組んで買い上げ、余裕を持った量を備蓄してきました。同研究所は、ワクチン類メーカーとしては唯一の公営企業。インフルエンザなど多くの病気のワクチンや抗毒素を手掛けてきました。しかし昨年11月、千葉県が行財政改革の一環で閉鎖を発表。3月末で製造ラインが全面ストップします。このため厚労省血液対策課は昨年末、業界団体を通じ、ワクチン類をつくる各社に抗毒素製造への協力を求めましたが、まだ後継メーカーは決まっていません。高度な技術や設備が必要な半面、患者発生が少なく、採算をとりにくいことが背景にあるとみられています。
- 資生堂は、メラニンの生成を抑えシミ・ソバカスを防ぐ「美白」と「肌あれ防止」の2つの効果を有する医薬部外品の新規有効成分として、「t-AMCHA(ティーアムチャ)」(t-シクロアミノ酸誘導体)の開発に成功、2月4日に厚生労働省より医薬部外品の新規有効成分として承認を受けました。本有効成分を配合して、美容液「クレ・ド・ポーボーテセラムブランエクストラAC」(医薬部外品、40ml、8,000円)を5月21日に発売します。強い紫外線を浴びると表皮角化細胞から「紫外線をあびた」という情報伝達物質が出されます。この情報伝達物質は表皮基底層にあるメラノサイト(メラニン生成細胞)に到達すると酵素チロシナーゼが活性化し、メラニンが盛んに作られ、シミやソバカスの原因となります。これまでの美白有効成分の多くは、酵素チロシナーゼに直接作用することで、メラニンの生成を抑えています。資生堂は、メラノサイトヘメラニン生成を指令する情報伝達物質のひとつである「プロスタグランジン」の生成を抑えるのに有効な「t-AMCHA」を開発。この物質は紫外線や乾燥などの刺激によって活性化されるタンパク質分解酵素「プラスミン」の生成を抑制する効果もあって、肌あれを防止することができます。「t-AMCHA」を配合した乳液を成人女性60名(33歳〜53歳)に朝晩1日2回、3ヶ月使用してもらい、有効性試験を行ったところ、シミ・ソバカス、くすみの悩み、肌あれに対する改善効果が認められました。■問い合わせ先■資生堂 お客さま窓口 TEL:0120-81-4710(フリーダイヤル)
- 一回投与すれば劇的に食欲が低下し、体重が減るという物質を米ジョンズ・ホプキンズ大医学部などの研究グループがマウスの実験で突き止めた。この物質は脂肪酸合成酵素の働きを抑制する化合物C75。食欲を感じる脳内物質の働きを抑制する作用もあるということです。同グループのダニエル・レーン博士らは、普通のマウスと遺伝子組み換えで肥満化したマウスにC75を投与。肥満マウスではその後5日間にわたり、90%以上も食事量が減少しました。C75を投与されていないマウスでも、えさを同量にするとやせますが、そのやせ方は投与マウスより24〜50%も少なくなっていました。このため、C75には食欲抑制だけでなく、カロリー消費の促進効果もあるとみられます。一方、普通のマウスは1日で食欲が戻り、その後のC75投与にも反応せず、投与を打ち切った後は過食現象もみられたということです。
- ダイエット食品の原料などになるガルシニアという植物の乾燥粉末(パウダー)に、動物実験で精巣への毒性が確認され、厚生労働省は、健康食品など高用量を継続的に摂取するものは、過剰摂取に気をつけることなどを情報提供するよう、業界などに要請することを決めました。国立医薬品食品衛生研究所の中間報告によると、ラットの飼料に5%の割合で乾燥粉末を混ぜて食べさせる実験で、半年後と1年後のオスの精巣に浮腫や委縮がみられ、影響の出ないレベルは1%程度と推定されました。動物実験のデータを人に当てはめた場合、市販のダイエット食品の1日の摂取目安量の10倍程度を超えると、影響が出る恐れがあるということです。ガルシニアは南アジアに自生する常緑樹。果皮に含まれるヒドロキシクエン酸に、脂肪をつきにくくする働きがあると報告され、ダイエット食品として注目されています。
- カネボウは、ラズベリー(ヨーロッパキイチゴ)の香気成分「ラズベリーケトン」に、皮下脂肪を減少させるダイエット効果があると発表しました。成分を配合した錠剤の健康食品(1錠1000個分)と体にはるシートを5月に発売します。同社は、脂肪の分解促進作用で知られる唐辛子の辛味成分「カプサイシン」の分子構造に着目。調査した結果、ラズベリーケトンに3倍の作用があることを発見しました。社員を対象にした試験では、毎日12錠を1週間飲み続けた34人のうち7割の人の体重が平均1キロ減り、太ももに1カ月シートをはった25人は皮下脂肪が平均5%薄くなったということです。
- 妊娠初期に魚介類を多く食べた人は早産しにくいという調査結果をデンマーク疫学センターの研究班がまとめました。魚に含まれる脂肪酸の働きが関係しているとみられます。研究班は魚をよく食べる地域で早産が少ないことに注目。これを医学的に裏付けるため、ユトランド半島東部の都市で、妊婦8729人に妊娠16週間までに魚介類をどれだけ食べたかを聞き、摂取量に応じ6グループに分類。出産状況を追跡調査しました。妊娠37週以前の早産の発生率は、魚介類を全く食べなかったグループが7.1%だったのに対し、魚を1日平均38グラム食べていた最多摂取グループは2.9%と半分以下。体重2500グラム未満の低体重児の割合はそれぞれ7.1%、2.1%でした。他のグループでも魚の摂取量が増えるほど早産が減り、出生児の体重が増えました。研究班は、1日15グラムの魚(脂肪酸で0.15グラム)を食べるかどうかで大きな差が出ると分析しています。
- ビタミンやミネラルに代表されるサプリメント(栄養補助食品)が伸びています。現在のサプリメント市場は年4000億〜6000億円とみられ、毎年数百億円の成長が続いています。
- 食物繊維や乳酸菌類など、体の機能によい影響を与える栄養成分を表示できる「保健機能食品」制度をめぐり、消費者に適切な情報提供などを行う「助言スタッフ」を業界などが養成する際の指針を、厚生労働省新開発食品調査部会がまとめ、公表しました。保健機能食品には、業者の申請を同省が許可する「特定保健用食品」と、高齢化や食生活の乱れなどで不足しがちな栄養分を一定量含んだものに表示を認める「栄養機能食品」の2種類があります。特定保健用食品だけで市場規模は4000億円を超えており、業界や企業には、店頭などでの情報提供担当者を増やす動きがあります。指針は、助言スタッフの主な対象者として、管理栄養士や薬剤師、保健婦といった専門職を想定。保健機能食品には栄養成分以外にも、人の生理的な機能に影響を与えるさまざまな成分が含まれていることを考慮し、適切な摂取方法や過剰摂取の防止について十分に理解しておくことが大切だと指摘しました。医薬品などと併用した際に悪影響がないかどうかの知識も必要だとしています。
- 狂牛病や遺伝子組み換え食品、脱法ドラッグなど、食べ物や薬に関する問題の増加に対応するため、東京都は4月から、米国の食品医薬品局(FDA)をモデルにした「食品医薬品安全部」(東京FDA)を新設します。人が摂取するものの安全に関する業務を一本化することで、行政の対応を迅速化し、危機管理を強化します。
- アヘンやヘロインの原料となるケシの栽培をやめさせようと、日本のNPO(非営利組織)がミャンマー北部の山岳地帯で、漢方薬の原料となる薬用植物の栽培を始めました。収穫後は日本の製薬会社に販売して現金収入の道を確保し、ケシ栽培をなくそうという狙いです。このNPOは、元厚生省国立医薬品食品衛生研究所生薬部長の佐竹元吉さん(61)が理事長を務める「ミャンマー・サブスティテゥショナリー・メディシナル・プラント・プロジェクト(MSMP)」(東京都港区)。佐竹さんは在職中、「黄金の三角地帯」と呼ばれるミャンマー、ラオス、タイの国境地帯の麻薬対策を担当する同省麻薬課から、「現地でケシに代わる作物は栽培できないか」と相談を受けました。ミャンマー北部は薬用植物の主産地・中国雲南省に近く、薬用植物なら定着する可能性が高いと考え、昨年3月、定年退職と同時に事業に取り組みました。早速、昨年5月と12月、中国国境に近いカチン州の山岳地帯にある約6ヘクタールの焼き畑跡地に、現地住民とともにシャクヤクやウコンの苗木を植えました。苗木は計100種類約800キロにも上りました。早く指導者を育て、苗木作りから収穫までを現地住民の手にゆだねたいと願う佐竹さん。「すべて現地で行うには10年はかかるが、夢はゴールデン・トライアングルという言葉をこの世からなくすこと」と話しています。
▲ 目次にもどる
微生物・生物
▲ 目次にもどる
香・環境
- 三洋電機はマイナスイオン発生装置を搭載した扇風機を発売します。◎主力機種◆品番 EF-30NHX1(L)◆メーカー希望小売価格(税別) 30,000円 扇風機本体下部からマイナスイオンを発生させ、マジックターン立体首振りでお部屋いっぱいに効率良くマイナスイオンを行き渡らせる「マイナスイオン立体風」を採用。本体から約1.5m(高さ0.8m)と離れた位置でも5000個/ccと、たっぷりのマイナスイオンを供給することができます。■問い合わせ先■三洋電機
- INAX(愛知県常滑市)は、シャープ(大阪市阿倍野区)と、世界初の空気浄化技術「プラズマクラスターイオン」を採用した、世界最小・満足最大のシャワートイレ『satis(サティス)2002年モデル』を共同で開発し、4月1日から発売します。INAXの『satis』は、世界最小サイズを実現したタンクレスの一体型シャワートイレ。日本で初めてJIS抗菌に適合した衛生陶器「ハイパーキラミック」と世界初の水アカ固着を防ぐ技術「プロガード」を採用しています。シャープの「プラズマクラスターイオン」は、プラスとマイナスのクラスターイオンを放出し、汚れた空気をきれいにし、さらにマイナスイオンを多く放出してリフレッシュ効果をもたらす世界初の空気浄化技術です。人がいない時はクリーンモードになり、プラスとマイナスのクラスターイオンをバランスよく放出し、浮遊カビ菌を分解除去。人がいる時はリフレッシュモードになり、マイナスイオンを多く放出します。クラスターイオンによる浮遊菌の除去効果は、マイナスイオンのみのときよりはるかに優れていることが実証されています。●価格…シャワートイレsatisD-118AS(床排水タイプ)280,000円[施工費・消費税別途]■問い合わせ先■INAXお客様相談センターTEL:0120-1794-00(フリーダイヤル)
▲ 目次にもどる
芸術・運動・心理
- 東京都八王子市の「上川病院」(吉岡充院長)が、演奏の経験がない痴ほう症の入院患者でも聴く人を感動させる合奏ができるようになる音楽プログラムに取り組んでいます。指導に当たっているのは合奏システム研究所の折山もと子代表ら。従来の音楽療法やレクリエーションの枠を超える本格的な音楽を目指して実践しています。ある日のプログラムでは、折山さんが「今日は山に入ります。裏山の竹に、そよ風や強い風が吹くとこんな音がするかなと思い浮かべながら楽器を鳴らして」と呼び掛け、一人ひとりがトーンチャイムという打楽器を思いのままに演奏するが、全体では風にそよぐ裏山の情景を織り上げました。昨年九月に始まって以来、患者はだんだん積極的になり、表現力や演奏のまとまりも出てきました。昨年12月には、院内で初コンサートを開き、成果をほかの患者や家族に披露しました。折山さんは「療法を超えて、演奏チームを育てる感覚で指導している。痴ほう症の人も音楽を通して残った感性を引き出せば、優れた演奏ができるはず」と話しています。
- 睡眠時間が1日7時間前後の人は最も長生きするとの調査結果を米カリフォルニア大サンディエゴ校の研究グループがまとめました。約110万人を対象にした初の大規模調査に基づくデータで、1日8時間以上の長い睡眠や4時間以下の睡眠不足は長寿には望ましくないということです。同校のダニエル・クリプキ教授らは82〜88年に、がん予防を目的に全米で実施された調査を基に、睡眠時間と死亡率との関連を分析しました。最も死亡率が低かったのは男女とも1日7時間(6.5〜7.4時間)睡眠の人で、睡眠時間が8時間の人は7時間の人に比べて、男性で12%、女性で13%死亡率が高くなっていました。9時間の場合は男性で17%、女性で23%、女性で10時間以上だと41%も死亡率が高く、睡眠時間が多くなるほど死亡率は高まりました。また4時間の男性は死亡率が17%、3時間の女性は33%高くなるなど、睡眠時間が少なくなるにつれて死亡率が高まる傾向も表れました。不眠を訴える人の死亡率は通常の人と違いがありませんでしたが、睡眠薬服用者は死亡率が10%以上高くなっていました。
▲ 目次にもどる
エコロジー・その他
▲ 目次にもどる
医学
基礎医学・免疫
- 免疫システムをコントロールする遺伝子・AIDが、免疫細胞以外の体細胞でも抗体の遺伝子組み換え(クラススイッチ)を引き起こすことを京都大の本庶佑(ほんじょたすく)・大学院医学研究科教授(分子生物学)や岡崎一美・大学院生らのグループが解明しました。細菌などの抗原が体内に侵入すると、免疫を作る細胞・Bリンパ球が抗体(免疫グロブリン=Ig)を作って攻撃します。AIDはその際、抗原の種類に応じてIg遺伝子の一部の組み換えを行い、4段階の発展型に変化して臨機応変に抗原を排除します。本庶教授らが実験で、これまでクラススイッチを起こさないとされていた非免疫細胞(マウスの線維芽細胞)にAIDを強制的に取り込んだところ、免疫細胞のBリンパ球と同じ確率でクラススイッチが起りました。このことから免疫系、非免疫系を問わず、あらゆる細胞で起こる、がんなど異常な細胞増殖の原因がAIDにある可能性が強まりました。
- 幹の太さが27センチ未満のスギに化学薬品のマレイン酸水溶液を注入すると花粉の基になる雄花の量を9割以上も減らす効果があることが、東京都の実験でわかりました。都は、ジャガイモの芽の抑制にマレイン酸が使用されていることに着目し、幼木で雄花の抑制効果を確認していました。その後多摩地区のスギ人工林の成木で実験を継続。昨年7月、スギの幹にドリルで穴を開け、約2000倍に薄めたマレイン酸の水溶液を注入して、雄花の重量を調べました。その結果、幹の太さが20センチ以上27センチ未満のスギにマレイン酸水溶液約1リットルを注入したとき、何も注入しなかった場合と比較して雄花の量を平均で9割以上抑制することができました。20センチ未満のスギでも同様の効果がありました。しかし、27センチ以上のスギでは安定した効果が出ませんでした。太さ27センチのスギは平均で植林してから約50年経過しているということです。
▲ 目次にもどる
遺伝子・体外受精・移植
- ひじやひざなどに激しい痛みを伴う慢性関節リウマチの発症に関係する遺伝子を、神戸大学医学部の塩沢俊一教授らが初めて突き止めました。塩沢教授は、慢性関節リウマチの患者が多い家系を中心に、患者1000人と、健常者500人の全遺伝情報を調べ、違いを比較。患者では「DR3」という遺伝子に異常が多いことを発見しました。微生物などを攻撃した免疫細胞は、役目を終えると自殺(アポトーシス)し、免疫の暴走を防いでいるが、このDR3遺伝子が働かないと細胞自殺が起きず、免疫細胞が過剰になって発症につながると考えられます。今回の遺伝子異常は、患者全体の2〜10%に見つかるということです。
- 指先にのる程度の小さな基板上で一度にたくさんのバイオ実験ができる装置を、東京大学の鳥居徹・助教授、樋口俊郎教授らが開発しました。液体を微小な粒状にした液滴を使い、従来装置より性能を高めました。少量のDNAで多数の実験をしたり、高価な試薬を節約したりするには、反応装置の小型化が欠かせません。これまで開発された装置の多くは、手のひらサイズ以下のガラス基板に溝をつくり、液体を流し込む方式です。樋口教授らが開発した方式は、まず絶縁フィルムを張った電極板上に油層を置き、独自の技術でつくった直径約1ミリの液滴をのせます。複数の液滴を静電気の力で動かし、目的の場所で衝突させてさまざまな化学反応を生じさせます。1センチ角程度の電極板でも実験が可能です。
- エモリー大学(米国ジョージア州アトランタ)のDavid Lynnたちが行った実験で、DNAが単独で次世代以降に遺伝情報を伝える能力があることが示されました。自己複製分子は、これまで人工的に合成するのに、二本鎖分子の一方を2つ使って分子の複製を行っていました。これに対してLynnたちは、塩基を1つずつ貼り合わせる方法をとりました。その結果としてできあがったのは、元の分子の複製ではなく、元の分子と相補的な分子でした。生細胞のDNA複製過程は酵素によって開始しますが、Lynnの研究グループは、酵素を使わずにDNA複製を開始させる方法を発見し、これにより1本のDNA鎖だけで、それと相補的なDNA鎖を形成させる鋳型として機能できるようにしました。こうして合成されたDNA類似体の鎖を構成する個々の塩基間の化学結合は、元のDNAの場合とは異なり、タンパク質を構成するアミノ酸の結合と同じアミド結合でした。アミド結合したDNA類似体の鎖は、本物のDNAでの塩基結合を触媒できます。
- 理化学研究所は、遺伝子組み換え技術を使って、アブラナ科の植物「シロイヌナズナ」を乾燥に強くすることに成功したと発表しました。植物の種子は、水分含有量が1〜5%にまで減少し、植物本体に比べ乾燥した状態になるが枯れてはいません。この種子には、ラフィノース属オリゴ糖という糖類が蓄積することが知られていました。理研の篠崎一雄主任研究員らは、オリゴ糖が植物本体も乾燥から守る働きを持っているのではないかと考え、シロイヌナズナの遺伝子を組み換え、オリゴ糖が植物体内で大量に作られるようにしました。遺伝子を組み換えていない野生のシロイヌナズナは、2週間乾燥状態に置くと、その後水をやっても枯れてしまいました。一方、遺伝子を組み換えた方は、2週間乾燥状態に置いても、その後水をやると生育を続けました。オリゴ糖が細胞膜や細胞内のたんぱく質と結びつき、乾燥により細胞が傷つくのを防いでいるようです。
- 品評会で優秀な成績を収めたチャンピオン豚の体細胞クローンをつくることに、米ウィスコンシン州のバイオテクノロジー企業「インフィジェン」が成功しました。同社はオス豚の耳の細胞の核を取り出し、核を取り除いた未受精卵に移植する方法で、クローン胚を作りました。これをメス豚の胎内に入れ、赤ちゃん豚を誕生させました。胎児ではなく成体の体細胞によるクローン豚の誕生は世界で初めて。
- クローン技術により生まれたマウスは、えさの量に関係なく、肥満体になる可能性が高いことが明らかになりました。米シンシナティ大学とともに研究を行ったハワイ大学のサカイ教授によると、普通に動き回り、一定量のえさのみを与えられていたにもかかわらず、クローンマウスは体脂肪が多く、肥満体になりました。9匹のクローンマウスを調べた結果、体脂肪量が多いだけでなく、肥満症状である血中のレプチンとインスリン濃度が高いことが判明しました。肥満体のクローンマウスの子供には肥満体質が遺伝しなかったということです。
- 米国の研究グループが、分化した成体細胞からのクローン個体作製が実際に可能であることを実証する道に先鞭をつけました。白血球のうち、免疫系で活躍するBリンパ球とTリンパ球から、クローンマウスを作製したのです。報告したのはマサチューセッツ工科大学ホワイトヘッド生物医学研究所のK
HochedlingerとR Jaenischで、彼らがリンパ球を使ったのは、これらの細胞が遺伝的なシャッフリング(DNAの切り混ぜ)を受けていて、クローン用細胞を提供する個体内の他の細胞と簡単に区別できるからです。Hochedlingerたちは、これらの細胞を再プログラムして胚性幹細胞に仕立て上げ、この細胞系から胚を発生させました。
- クローン人間を誕生させると公言している新興宗教団体ラエリアン・ムーブメント(拠点・スイス)が、不治の病で死に瀕している資産家の独身男性(59)を新たな候補に選んだ、と発表しました。男性は自分のクローンに資産の半分を与え、残り半分は子宮を貸してくれる女性に提供するということです。ラエリアンの当初計画にあった、事故で死んだ2歳児のクローンづくりについては、「米食品医薬品局(FDA)の圧力で米国内の研究所が閉鎖に追い込まれ、断念した」と説明しています。
- さまざまな組織に分化する能力があり、万能細胞と呼ばれる胚性幹細胞(ES細胞)をクローン技術で作り、遺伝子操作を加えた上で移植して、マウスの免疫機能を向上させる実験に、米国のホワイトヘッド・バイオメディカル研究所などのグループが成功しました。クローン技術を病気の治療に用いる可能性が指摘されていますが、実際の生物での成功は初めて。研究グループは、遺伝子の異常のために免疫機能が働かないマウスの皮膚細胞を採取。核を除去した別のマウスの卵細胞に移植し、培養して作成したクローン胚から、ES細胞を取り出しました。このES細胞の遺伝子の異常を修復し、皮膚細胞を提供した免疫異常のマウスに移植しました。ES細胞は免疫細胞に分化し、3〜4週間後には、移植前にはなかったリンパ球が血液中に確認され、免疫反応に関連する免疫グロブリンも作られていました。
- 滋賀医科大の鳥居隆三助教授(実験動物学)らと田辺製薬の共同研究チームは、サルの胚性幹細胞(ES細胞)に、クラゲの発光遺伝子を組み込むことに初めて成功したと発表しました。光を当てると緑色に光るため、生体のあらゆる組織に変わる能力を持つES細胞の分化が簡単に目で確認できます。クラゲのGFP(緑色蛍光性たんぱく質)遺伝子を、カニクイザルの受精卵からつくったES細胞に、細胞表面に電気で穴を開けて遺伝子を入れる電気穿孔法を使用して組み込みました。
- 心臓の筋肉、脂肪、骨などに効率よく変身させられる新しい種類の多能性幹細胞を、大人のマウスの骨髄から発見、特許を出願したと協和発酵が発表しました。
- 白血病の男児(5)の治療に必要な臍帯血を確保するため、両親が体外受精を行い、息子と白血球の型が一致する女児を妊娠、英国内の病院で2月14日、出産しました。無事に生まれた妹の臍帯血は、兄の再発に備えて冷凍保存されました。特定の目的で選ばれた体外受精児の出産は米国での例に続き世界で2例目です。
- 家族性の若年発症型アルツハイマー病に対する受精卵診断が、米国で行われたことが明らかになりました。米国の生殖遺伝学研究所(Illinois州シカゴ)が実施したもの。同研究所は昨年6月にも、癌抑制遺伝子であるp53遺伝子に対して受精卵診断を行ったことを発表しており、遺伝性疾患の受精卵診断は今回が2例目となります。受精卵診断(着床前診断)を希望したのは、姉の発病で家族性の若年発症型アルツハイマー病家系であることが判明した30歳の女性とその夫。アミロイド前駆蛋白(APP)遺伝子に変異があり、家系の発症パターンから、本人はおそらく30歳代でアルツハイマー病を発症することが予想されています。「子供には変異遺伝子を受け継がせたくない」という両親の強い希望で、同研究所は受精卵の遺伝子診断を実施。体外授精で得た受精卵から、問題の遺伝子変異がないものを母体に着床させました。産まれた子供には、遺伝子の変異がみられないことが確認できたということです。
- 通常では妊娠が難しい高齢女性の卵子と、若い女性の卵子の核を取り換えて卵子を若返らせ、受精させることに、東京都内の医療機関「加藤レディスクリニック」(加藤修院長)が成功していたことが明らかになりました。将来、倫理面、安全面の課題がクリアできれば、凍結保存させた受精卵を子宮に戻して妊娠させることも検討しています。日本産科婦人科学会は現在、第三者の卵子提供は認めていません。同クリニックでは昨年、不妊治療を行っている夫婦の同意を得て、あらかじめ核を除いた若い女性の卵子に、40代女性の卵子から取り出した核を移植。40代女性の遺伝情報を持つ「若返り卵子」を数個作りました。これを使って体外受精を行い、子宮に戻す直前の段階まで育てた受精卵を作ったということです。女性が高齢になると、卵子も老化するため、妊娠しにくくなることが知られています。原因は、核を囲む細胞質にあると言われ、動物実験などで、これを取り換えて妊娠させる試みが行われてきました。しかしこの方法は、卵子の核以外の部分にある卵子提供者の遺伝情報も、子供に引き継がれてしまうため、父母、卵子提供者の計3人の遺伝情報を持つ子供が生まれるという、倫理、安全両面の問題を抱えています。米国でも昨年、若い女性の卵子の核以外の部分を、高齢者の卵子に注入する方法で「若返り」を試み、赤ちゃんが生まれました。米国ではこの医療技術を人に使う場合に、国の承認が必要とされています。同クリニックは岩手大学と共同で、牛でも同様の方法を試み、2月19日午後にも子牛が生まれる予定とのことです。
- フランス初の試験管ベビーとして出生、2月24日に20歳の誕生日を迎えた女性が同日付仏日曜紙ジュルナル・デュ・ディマンシュの紙面で素顔を明かしました。女性は科学を専攻する大学生のアマンディーヌさん(20)。82年2月24日にパリ郊外の病院で生まれた際には「奇跡の子」として話題をさらい、詰めかけた報道陣の目をそらすため母親は地下通路から、赤ん坊は別の女性に抱かれて玄関から病院を出ました。以来、匿名に守られてきました。匿名のベールを自ら脱ぎ捨てた理由をアマンディーヌさんは「自分を守る一方で特別な存在にしていた匿名の重荷から解放されたかった。それにもう自分の運命に責任を持てるようになったと感じているから」と説明。「私は(人工授精の)『快挙』なんかでなく、今、ここに存在している」と語りました。「いつか、困っている人を手助けする人道的な仕事に参加する」のが夢だということです。
▲ 目次にもどる
脳・心
- カプサイシン(唐辛子の成分)は、高温にも反応するイオンチャネルを活性化することで、焼けつくような痛みをもたらします。今回、メントール受容体のクローニングから、ミント(はっか)がなぜ「ひんやり」と感じられるのかが説明づけられました。この受容体は、低温によっても活性化するのです。カプサイシン受容体とメントール受容体は構造が似ていることから、感覚神経の終末は共通の分子レベル機構を使って高温と低温を感知していることが示唆されます。
- 耳は、音の信号を2つの成分に分解しています。1つはゆっくりと変動する「包絡線」成分、もう1つは速く変動する「微細構造」成分です。マサチューセッツ眼科耳鼻咽喉科病院(米)のZ
M Smithたちの報告によると、包絡線は主に発話を聞き分けるために使われるということです。微細構造のほうは音の高低の聞き取りや音源の定位にかかわっています。
- 色から形へと、注意の向け方を変えるとき、ヒトもサルも脳の同じ部位が活動していることが初めて東京大学医学部と岡崎国立共同研究機構生理学研究所の合同研究グループの実験で明らかになりました。東大医学部の研究員、中原潔さんらはニホンザル2頭に、色と形が異なる複数のマークを使って実験。最初に、同じ色のマークを選ぶ訓練をしばらく続け、その後、今度は形の同じマークを選ばせる訓練に移行するとき、脳のどこが活動しているかを機能的MRI(磁気共鳴画像化装置)で観察しました。次に協力者に同様の課題をやってもらい、機能的MRIで調べました。二つの結果を比較したところ、ヒトもサルも、前頭葉の一部が同じように活性化していることがわかりました。
- 脳内で数を勘定する役割を担う神経細胞を東北大学医学部の丹治順教授たちがニホンザルを使った実験で突き止めました。大脳上部の「頭頂葉」と呼ばれる部分にあり、勘定する時だけ働くということです。まず、ニホンザルに実験室でレバーを握らせ、「押す」動作を5回、それに続いて「回す」動作を5回繰り返すよう訓練しました。動作の回数を覚えないとできない行為で、これを習得させた後、脳にセンサーを入れ、動作中の神経細胞の活動を観察して、回数を勘定する細胞があるかを脳の複数の場所で調べました。その結果、頭頂葉の細胞が強く反応。しかも、この部分の細胞は、活動を分析した125個中46%が5回の繰り返しのうち1度だけ、54%が例えば3回目と5回目など複数の動作の際に応じて活動しました。これらを組み合わせて脳は回数を勘定しているようです。
- ドイツのヴュルツブルグ大学のMartin Heisenbergらは、ハエの標準的な脳の大きさを測定しました。この結果、ショウジョウバエの頭の大きさは、ハエの脳の平均的な大きさは、縦の長さは髪の毛の太さ2本分、横は5本分で、かなり一定していることを発見しました。研究チームは120個の脳を解剖し、その寸法を3次元顕微鏡を使って測り、特別設計のソフトウエアでその映像を比較し、平均的な大きさを割り出しました。脳の平均的な形と大きさが分かるということは、脳にわずかな欠陥があるハエをも見分けることができるようになるということです。人間でも国際脳機能マッピングコンソーシアムをひきいる、カリフォルニア大学ロサンゼルス校のJohn
Mazziottaは、7000人近い人の核磁気共鳴画像(MRI)を使って、人間の「標準的な脳」というものをはっきりさせたい考えで、人間の「標準的な脳」は2003年9月までに完成する予定です。
- 帰巣性のあるハトの海馬の神経細胞が、その周辺環境の学習に極めて敏感であることを米国の研究者が発見しました。ボウリンググリーン州立大学(米国オハイオ州)の神経科学者Verner
Bingmanの研究チームは、ハトとラットの複数の脳細胞にそれぞれ電極を挿入し、部屋を歩き回る時の脳細胞の活動を記録しました。その結果、ラットの脳は比較的単純明快で、部屋の隅にいるときに発火する脳細胞と部屋の中央部で活発に動きまわっているときに発火する脳細胞がありました。ハトの海馬細胞の発火パターンは、これよりも複雑で、原因要素は位置だけではありませんでした。ハトの場合、現在位置を割り出すためにラットよりも多くの視覚情報を取り入れている可能性があるとBingmanは考えています。
- オットー・フォン・ゲーリック大学(ドイツ、マグデブルグ)のThomas Munteらの研究で、バイリンガルの人たちは、その時しゃべっている言語に属さない語を、その単語の意味を理解する前の段階で排除していることが明らかになりました。Munteらはスペイン語と、スペイン北東部で使われているカタロニア語の両方に堪能な人たちについて調査を行いました。被験者にはスペイン語とカタロニア語、および意味を持たない偽単語からなるリストから、スペイン語の単語を選び出すという作業をやってもらいました。二カ国語を使う人たちでは、普通に使われているカタロニア語の単語が、希にしか使われない単語の場合と同じ脳の活動を引き起こしました。バイリンガルでは、単語を排除する前に、その語の意味を考えることは行われず単語の点検が行われます。カタロニア語と偽単語を排除する際には、単語を読むのに関わっている脳の領域が活動していることが、機能的磁気共鳴画像法(fMRI)画像から明らかになりました。スペイン語、あるいはカタロニア語の発音の規則がフィルターとして働き、使われていない方の言語に属する語を識別している可能性があるようです。
- 赤ちゃんがおなかの中で母国語を学んだことが示されました。日立基礎研究所主管研究長の小泉英明さんらは、仏国立認知科学研究所と共同で、生後5日目の赤ちゃんに「母国語」と「母国語の逆回し」を聴かせる実験をしました。脳の活性度を調べると、母国語に対しては、大人が言葉を聴くのと同様、左脳の言語野が強く活性化しました。一方の「逆回し」では、左右の脳が同程度に活性化し、意味のない音と認識していました。
- 高齢者の記憶力は、訓練によって、ある程度回復可能なことを示す研究成果を米ワシントン大の研究チームがまとめました。記憶力の低下は必ずしも脳細胞の破壊が原因ではなく、脳の特定領域のつながりが悪くなるために起こると推定されるということです。ランディ・バックナー助教授らのチームは、20歳代と70〜80歳代の健康な62人に複数の言葉を覚えてもらい、思い出すテストを実施。MRI(核磁気共鳴映像)装置を用いて、脳のどの領域が働いているかを調べました。その結果、若い人の脳では、まず脳の右前頭部が働き、直後に左前頭部が働いていました。しかし、高齢者は左側の領域をほとんど働かせていませんでした。だが、研究チームが、言葉の意味をよく考えたりイメージを意識するなど関連づけて覚える訓練を施した後のテスト結果では、高齢者の脳左前頭部も、若い人並みに働いていたということです。
- 哺乳類の成体でも脳の海馬で新しい神経細胞が作られることが知られていましたが、これらの細胞が本当に完全な機能をもつ脳細胞になるのかはわかっていませんでした。今回ソーク生物学研究所のF
Gageたちは、成体マウスの海馬で新しく作られた細胞が、脳細胞と同じような性質を示し、神経信号を発するとことを見いだしました。
▲ 目次にもどる
臨床医学(病態・診断・治療)
- 代表的な小児がん「神経芽腫」が自然治癒する仕組みの一端を、国立がんセンター研究所や神奈川県立こども医療センターなどの共同研究チームが解明しました。神経芽腫は白血病に次いで多い小児がんで、腎臓の上の副腎や、背骨の左右に広がる交感神経節に病巣ができます。死亡することもある半面、病巣が自然に縮小したり消えたりする例も多くあります。患者110人のがん組織の自然治癒した部分を調べたところ、ras遺伝子が活性化し、従来にない仕組みで自殺している細胞群が見つかりました。培養がん細胞で人為的にras遺伝子を働かせ、同様に自殺することも確かめました。
- 乳糖不耐症を遺伝子の面から調べると、本来は人類の多くが持つ性質で、大人になっても大量の牛乳が飲めるのはむしろ遺伝子の突然変異に由来するという研究が発表されました。カリフォルニア大学ロサンゼルス校の女性遺伝学者リーナ・ペルトネン博士らは、フィンランド在住の9家族196人の乳糖不耐症の人を調べました。その結果、乳糖を分解する酵素に関係し、乳糖不耐症の原因になっている遺伝子を見つけました。さらに、この遺伝子についてヨーロッパ、アメリカ、アジアから、いろいろな人種、民族の血液サンプルを集めて調べたところ、遺伝的に離れた人種でも、同じ乳糖不耐症の人には共通して見つかりました。このことより博士らは、乳糖不耐症の遺伝子は人類発祥の古い時期からあると結論づけました。乳糖不耐症の遺伝子が人類に共通している基本的な遺伝子であるとすると、大人でも牛乳を多く飲める欧米人が持つ遺伝子は突然変異で得られたということになり、突然変異を起こした時期については、おそらく1万年から1万2000年ほど前だろうと研究者たちは推定しています。
- 健康な高齢者の血圧は気温と強く逆相関することが、香川医科大学総合診療部の木村敏章氏らが、香川県東部に住む15人の高齢者を対象に、3年間にわたって家庭内で測定した血圧データを分析した結果わかりました。対象者は、在宅健康管理システムを利用している高齢者のうち、高血圧症との診断やその治療を受けていない15人(男性7人、女性8人、平均年齢80歳)。15人の全データの平均値を月ごとに求め、気温との関係を調べたところ、強い相関関係がありました。気温を摂氏x(度)、収縮期血圧y1(mmHg)と拡張期血圧y2(mmHg)とすると、気温と血圧の回帰式はy1=−0.48x+130.3、y2=−0.29x+80.8でした。相関係数rはそれぞれ0.972、0.984と高く、月ごとの収縮期血圧のばらつき(標準偏差)をみると、夏よりも冬の方がやや大きかったということです。
- 痴呆を起こすアルツハイマー病や、クロイツフェルト・ヤコブ病などの神経難病は、水に溶けにくいたんぱく質が脳の神経細胞に蓄積するという特徴が共通します。九州大大学院薬学研究院の井本泰治教授(免疫薬品学)らは、たった1個のアミノ酸が変化することで、たんぱく質の立体構造が変わり、水に溶けにくくなることをつかみました。研究グループは、ニワトリの卵や風邪薬に含まれるリゾチーム(たんぱく質)のアミノ酸の並び方を変えながら、核磁気共鳴(NMR)と呼ばれる特殊な装置を使って構造を調べました。その結果、129個並んでいるリゾチームのアミノ酸のうち、62番目のアミノ酸であるトリプトファンをグリシンに変えると、リゾチームの構造が大きく変化することを発見。この構造変化で水にほとんど溶けなくなることを確認しました。この構造変化は、大半のたんぱく質に共通するとされます。神経難病でのたんぱく質の異常も、一つのアミノ酸の変化がきっかけになっている可能性が高いということです。
- 急性中耳炎の後、中耳に浸出液がたまって聞こえが悪くなる「浸出性中耳炎」の発症に、胃液の逆流が関与している可能性があることがわかりました。浸出性中耳炎の小児の浸出液を調べたところ、8割以上で胃液の成分がみられたということです。英国Newcastleupon
Tyne大学生理学部門のAndrea Tasker氏らは、2〜8歳の浸出性中耳炎の小児54人から浸出液を採取し、胃液の成分の一つであるペプシンが含まれているかどうかを酵素免疫法(ELISA法)で調べました。その結果、54人中45人(83%)で、浸出液にペプシンが含まれていることが判明。ペプシン(ペプシノーゲン)は血清中にも含まれていますが、浸出液のペプシン濃度は血清中の濃度の1000倍以上で、このペプシンが血清からではなく胃液由来のものであることが明らかになったということです。胃液の逆流が浸出性中耳炎を引き起こす原因として、研究グループは「上咽頭を通って中耳に流れ込んだ胃液が、耳管や中耳の粘膜を一過性に傷害して炎症を引き起こし、そこが細菌の二次感染の温床となる」と推察しています。
- 佐久総合病院総合診療科の下島卓弥氏らの調査によると、うつ病といった精神疾患や心理的要因などが体重減少の原因であることは珍しくないようです。下島氏らはカルテを使って後ろ向きに調査しました。対象患者は、1999年1月から2000年12月までに、同病院の総合外来を新患で訪れた1万2722人のうち、体重減少を主訴あるいは主要症状の患者98人。内訳は男性41人、女性57人で、年齢層は10歳代から80歳代まで幅広く分布しており、50歳代が最も多くなっていました。患者の原因疾患については、精神疾患・心理的要因が最も多く29人(29.6%)、2番目に多かったのは内分泌・代謝性疾患の20人(20.4%)、以下、感染症、消化器疾患、呼吸器疾患と続き、悪性疾患は、わずか3%に過ぎませんでした。先行研究と比べて悪性疾患の割合が低かったことについて、下島氏は、「これまでの欧米諸国における発表は2次もしくは3次医療機関におけるもの。われわれの病院とは患者層が異なっていたのだろう」と語りました。
- プロテオミクス技術の臨床応用を目指し、昨年7月に米国食品医薬品局(FDA)と米国国立癌研究所(NCI)が共同でスタートしたプロジェクトに、早くも大きな成果が出ました。感度100%、特異度95%で、卵巣癌を30分で血液診断する技術を確立したということです。「プロテオミクス」は、プロテオーム解析に代表される、蛋白を系統的・網羅的に解析する技術のことです。「プロテオーム」は、ゲノム(細胞内の全遺伝子)に対応する造語で、「細胞内の全蛋白」を表す言葉。プロテオーム解析では、二次元電気泳動法で試料中の全蛋白を展開し、スポットごとに蛋白分解酵素でペプチド断片を作って質量解析を行う手法が用いられます。FDAとNIHは1997年から、癌細胞などのプロテオーム解析を進めており、昨年7月にはこれまでの研究成果を臨床応用する「Clinical
Proteomics Program」プロジェクトをスタートしていました。今回発表された研究結果は、卵巣癌の血液診断に関するものです。まず、卵巣癌患者50人と、卵巣癌にかかっていない健康な女性50人の血液について、プロテオーム解析を実施。卵巣癌に特徴的な解析パターンをクラスター分析し、「卵巣癌に特徴的なプロテオーム解析のパターン」を同定しました。次に、同定されたパターンを用い、116本の血清試料を分析。卵巣癌か否かを診断しました。116本の血清試料の内訳は、卵巣癌患者由来が50本、健常人由来が66本でしたが、患者由来の試料についてはすべて「卵巣癌」と判定。うち18本は、早期癌(病期1)患者から採取したものでした。健常人由来の66本については、3本を「卵巣癌」と誤診しましたが、63本は正しく「癌ではない」と診断しており、検査精度は感度100%、特異度95%となりました。注目すべきなのは、陽性反応的中度(陽性者が実際に疾病を持っている割合)が94%と極めて高い点。研究グループは今回の試料を用い、卵巣癌の血液検査として通常用いられる炭化水素抗原125(CA125)についても精度を調べていますが、この陽性反応的中度は34%で、このことから、従来の検査手法と比べ、プロテオミクス技術を用いた検査法が、スクリーニング検査法としても格段に優れていることが示されました。
- 愛知県小牧市の小牧市民病院(末永裕之院長)は、脳の磁場を探って、てんかんの発作原因や脳腫瘍の部位を正確につかめる「脳磁図検査」を2月18日から導入します。同病院ではこの検査と、開頭手術をせずに治療できる放射線治療装置「ガンマナイフ」とを併用し、メスなしで正確に治療できる全国初の体制を確立する方針です。脳磁図は、脳内の神経を流れる電気に伴う微弱な磁場を画像処理したもので、視覚や言語など脳内の役割分担を解析できますが、脳の機能研究以外ではあまり使われていませんでした。だが、コンピューター断層撮影装置(CT)の画像などと重ね合わせると、てんかん発作の発生場所などを特定できることがわかりました。また同病院は91年に国内で初めて「ガンマナイフ」を脳外科治療に導入しましたが、脳磁図と併用すると、てんかんや脳腫瘍の根本的な治療を正確に行える可能性が高いことがわかりました。
- 上腕骨外側上顆炎(いわゆるテニス肘)の患者を対象とした無作為化試験で、ステロイドの局所注射は、短期的な治療効果は高いが長期的には理学療法や保存療法よりも予後が悪いことがわかりました。テニス肘の治療法には、外科手術を除けば(1)ステロイドの局所注射、(2)抗炎症薬などの処方で様子を見る保存療法、(3)理学療法−−の3つの選択肢があります。オランダVU大学医療センターのNynke
Smidt氏らは、地域の家庭医の協力を得て比較研究を実施しました。6週間後の治療成功率は、ステロイド局注群で92%、保存療法群で32%、理学療法群で47%となり、短期的にはステロイド局注群が最も治療成績が良いことがわかりました。ところが、6週の治療期間が終了すると、ステロイド局注群では症状が再燃するケースが続出。結局、治療開始から52週が過ぎた時点では、ステロイド局注群の治療成功率は69%にまで落ちてしまいました。一方、理学療法群では91%、保存療法群では83%の人で治療が成功しており、長期的には保存療法や理学療法の方が治療成功率が高くなることが明らかになりました。ステロイド局注群で治療の長期成績が悪い点について、研究グループは二つの理由を考察しています。一つは、ステロイドの局注が腱を直接傷害するというもの。もう一つは、ステロイドの局注で劇的に痛みが治まるため、患者が「痛みを起こすような動きを避ける」という医師の指導を守れず、腕を使いすぎてしまうというものです。
- 骨折部位に低出力の超音波を断続的(パルス状)に当てる「超音波骨折治療器」に、治癒日数を64日間短縮する効果があることが、カナダMcMaster大学臨床疫学生物統計学部門のJason
W. Busse氏らによる3臨床試験のメタ分析から明らかになりました。ただし、骨止め処置など観血的な治療を行っている場合、治癒日数の短縮効果があるかどうかは不明だということです。
- 体の一部がまひした男性が、脊髄への弱い電気刺激のおかげで近所の店まで歩いて行けるようになりました。アリゾナ州立大学テンピー校のRichard
Hermanたちは、車いすなしでは動けない四肢まひの人を動いているトレッドミル上で支えてやり、一定のリズムで歩く作業を手助けしました。この人はゆっくりと50メートル歩けたものの、とても消耗しました。ところが、背中の低い位置にペンほどの太さの電極を埋め込み、歩く際に脊髄に電気刺激を与えると、歩くのにかかる時間が大幅に短くなりました。数カ月の訓練の後、この患者は1キロも歩けるようになりました。
▲ 目次にもどる
東洋医学・代替医療・養生
▲ 目次にもどる
倫理・その他
▲ 目次にもどる
オーリング原理・科学・情報処理
- ベルギーのアントワープ大学のRWilsonたちは10種類の決められた種目で総合得点を競い合う、十種競技の男女選手の成績を統計的に処理し、ある特定の種目で最高得点を上げた選手は、概してその種目と「反対の性質を持つ種目」での得点が最低になることを見出しました。たとえば、砲丸投げで最高の成績を取った者は、1,500メートル走の成績が最低でした。また、ある一分野でどの位優秀かが、それ以外の分野の総合的能力に直接影響することもわかった。たとえば、十種競技100メートル走で世界最高となった選手は、他の9種目では平均以下であった。研究者たちは、「種目別能力特性」の進化についてさらに解明が進めば、十種競技のトレーニング形態をもっと効率的にできるかもしれないと述べています。
- 元素の種類が変化する奇妙な反応が見つかりました。三菱重工業基盤技術研究所が行った実験で、パラジウム(Pd)という金属を主成分とする多層膜に重水素(D2)ガスを通すと、膜表面に添加したセシウム(Cs)がプラセオジム(Pr)に、ストロンチウム(Sr)がモリブデン(Mo)に変わったということです。ある元素が別の元素に変わる反応は、核分裂や核融合を伴うのが普通です。ところが今回の実験の反応条件は1気圧、70℃。三菱重工の試算によると、わずか数eVの小さなエネルギーで元素の種類が変わったことになります。実験装置も比較的単純です。金属容器をPd多層膜で仕切り、片側に重水素ガスを入れ、もう一方は真空にします。ガス圧によって、重水素は徐々に多層膜を透過していきます。重水素ガスを透過させた後、膜表面をX線光電子分光分析器で調べたところ、Cs(原子番号55)がPr(同59)に、Sr(同38)がMo(同42)にそれぞれ変わっていたということです。別の元素に変わるメカニズムや理論はまったくわかっていません。三菱重工は試料や装置を提供し、今後多くの研究者に再現性を確認してもらう考えで、すでに大阪大学や北海道大学、岩手大学などで研究が始まりました。また、海外でも米国のイリノイ大学や米ベンチャー企業のCETIなどが三菱重工とは独立に同様の実験に取り組んでいるということです。
- 英バイオテクノロジー(生物工学)会社PPLセラピューティクスの研究者アラン・コールマン博士といえば、世界初のクローン羊「ドリー」の生みの親として知られますが、英紙フィナンシャル・タイムズは、同博士がシンガポールの会社に引き抜かれたと報じました。同博士は、PPL社を2月末日付で退職。シンガポールに拠点を置き、人間の臓器などに分化し得る胚性幹細胞(ES細胞)を研究するESセル社に転職します。
- タニタ(東京都板橋区)では、体重・体脂肪率に加えて、その人自身の体組成に基づいた基礎代謝量が計れる基礎代謝チェック付き脂肪計『メタボディ』を、本年3月1日より発売します。基礎代謝とは生きていくために最低限必要な基礎的なエネルギーのことです。『メタボディ』は、体重(100g単位)や体脂肪率(0.1%単位)に加えて、基礎代謝量(1kcal単位)を測定でき、あなたのカラダが「(脂肪の)燃えやすい」体質なのか「燃えにくい」体質なのかをひと目でわかり易く判定します。基礎代謝量は、生体インピーダンス法を採用し、単なる体重からの測定値ではなく、その人自身の体組成に基づいた高い精度の測定値でカロリー表示します。◆希望小売価格17,500円(消費税別)◆販売:全国の有名デパート、専門店、量販店、ドラッグストア、ディスカウントストア、ホームセンター等■問い合わせ先■TANITAお客様サービス相談室 TEL:03-3967-9655(受付時間平日9時から17時)
- 東芝は、腕に装着したセンサーで脈拍や運動量などを測り、PDA(携帯情報端末)で健康状態を常に管理できる新システムを開発しました。長時間仕事を続けたり、ストレスがたまると「休憩しましょう」と呼びかける警告機能もあります。新しいシステムは、腕時計型のセンサーで測ったデータを無線で送信し、PDAの画面でリアルタイムの健康状態を表示します。PDAから病院にデータ転送すれば、かかりつけの医師が患者の健康状態を監視することもできます。同社は2005年までに実用化を目指しており、レンタルでのサービスなどを検討しています。
- 米フロリダ州のハイテク企業アプライド・デジタル・ソリューションは、人体埋め込み用のコンピューターチップの商品化に向け、米食品医薬品局(FDA)に近く、認可申請手続きを取ることを明らかにしました。米粒大のチップには病歴などあらゆる個人情報を入力することが可能で、普及すれば、病院に運び込まれた意識不明の患者を治療する際などに役立つと同社は期待していますが、プライバシー保護の観点から新たな懸念も浮上しています。
- 独居老人がテレビのリモコン操作でお願いごとをすると、インターネットでボランティアの携帯電話に送信され、都合のいい人が駆けつける。こんなシステムを開発したのは、医療コンサルティング会社「シナジー」(品川区)。毎日安否を確認する「お元気コール」と、生活の中の困りごとを24時間支援する「ホームサービス」があります。ホームサービスは、「お話し相手」や「簡単なお手伝い」を依頼できます。ボランティアは事前に都合のいい日時や協力できる項目を本部に登録してあり、条件にあった人の携帯電話に自動的にメールが送信されます。昨年12月から2月末まで、NPO(非営利組織)「生活・福祉環境づくり21」(千代田区)とともに独居老人ら20人、中学生らボランティア100人の協力をえて足立区内で実験を実施しています。
- NTTと、福岡市立こども病院、九州システム情報技術研究所は、同病院に長期入院している小児患者が、自宅にいる家族といつでもパソコンでテレビ電話ができるシステムを導入し、子供のさびしさや不安感の解消に役立てるための共同実験を3月中旬から実施すると発表しました。実験に参加するのは幼稚園児から小学生までの入院患者。光ファイバーのブロードバンド(大容量高速)通信で病室と自宅を結び、「今話せる」「外出中」など、お互いの状況を知らせ、相手の顔を見ながら会話もできます。また、院内学級の教諭が複数の子供に同時にネットで教える仮想授業も行います。
- 四国四県の約80の医療機関がこのほど、患者の医療情報を電子データ化した電子カルテを共有化するシステムを導入しました。県境を越えた電子カルテのネットワーク化は全国で初めて。経済産業省のモデル事業として、四国の各県や医師会、大学が約3億円かけてシステムを開発。電子カルテは、医療機関によって記録方式が異なり、共有化は困難とされていたが、インターネット上の新たな共通言語XMLを採用することで解決しました。
- パッケージソフトウエア開発のアシスト《http://www.ashisuto.co.jp/》(東京都港区)はこのほど、携帯電話で病院の診察予約ができる、病院向けソフト「Medi
Qube(メディ・キューブ)」の販売を始めました。メディ・キューブは、病院を利用する人が24時間どこからでも、携帯やPHS、PCなどを使ってインターネット予約ができるシステム「診察予約」と、病院スタッフのスケジュールを管理し、院内情報を共有できる「グループウエア」で構成されています。診察予約では、希望日時の予約を入力すると、可能かどうかを○×で瞬時に通知。予約を忘れないよう、前日に「明日診察があります」というメールを受け取れるほか、受診当日にあと何人かを調べたり、「何人(人数の設定が必要)待ちになりました」という呼び出しメールを受け取ることもできます。一方、グループウエアには、掲示板機能を搭載、医師や看護士などスタッフ間で、スケジュールや院内情報を共有できます。価格は5年間のリース契約に換算すると月額3万8000円程度となり、保守料金を加えても同6万円を切る計算だということです。既に、兵庫県西宮市の市立中央病院の小児科で試験サービスを始めており、4月1日から本格稼動します。
- 岩手県は、県内の医療機関によるがんや脳血管疾患の手術実績などを、県のホームページに掲載することを決めました。医師会などに同意を求める作業を進めており、早ければ4月から実施する予定です。対象は県内に約200ある病院と診療所で、患者がニーズに沿った身近な医療機関を選べるほか「かかりつけ医」からの専門機関への紹介をスムーズに行えるようにします。公表するのは2000年度に県が実施した医療機能調査の結果で、がんのほか不妊治療やアレルギー疾患の治療実績などです。
▲ 目次にもどる
医療
- 米ボルティモアのジョンズ・ホプキンズ大病院は、オリンパス光学工業が製造、販売した気管支内視鏡に欠陥があり、肺に緑膿菌が感染した可能性があると、内視鏡検査を受けた患者400人以上に通知したと発表しました。同病院によると、肺の検査を受けた患者のうち約100人が菌の陽性反応を示しました。うち2人が肺炎で死亡しましたが、欠陥が死因かどうか不明としています。問題の内視鏡は口金がゆるんで細菌が繁殖しやすくなっていました。同社によると、内視鏡は米国、日本、欧州などで約1万4000本が販売され、既にリコール(無料の回収・修理)の通知が出されています。米疾病対策センター(CDC)によると、同社は昨年9月に問題に気付き、同11月末にリコールを決め、米食品医薬品局(FDA)と全米の医療機関2360カ所に通知しました。同病院は、リコールの通知方法に問題があり、内視鏡を使う部局は今年2月上旬まで欠陥を知らされなかったと主張。CDC当局者は「リコール手続きは適正だった」としながらも、リコールの事実をホームページに載せなかったため十分な効果を持たなかった、との見方を示しました。オリンパス光学工業広報室によると、米国以外では、日本を含め気管支内視鏡の緩みが原因となった健康被害発生は報告されていないということです。
- 東京女子医科大病院(東京都新宿区)の心臓手術ミスで群馬県高崎市の平柳明香さん(当時12)が死亡した問題で、医師らが手術に使った人工心肺装置の仕組みを知らなかったため、手術中に生じた装置のトラブルに対処できなかったことが、関係者の話でわかりました。同病院の人工心肺の方法は3種類あり、「ポンプ脱血法」「落差脱血法」「陰圧吸引補助脱血法」で、明香さんの手術では「陰圧法」が採用されました。しかし、関係者によると、手術の責任者の医師らは「陰圧法」が同病院で採用されていることを知らされず、明香さんの手術では「落差法」を採用したと認識していました。両方法の装置は、外見上はほとんど違わないということです。病院側が設置した調査委員会の調査報告書は、明香さんの死亡原因を、心臓付近の血液を吸引するポンプの回転数を長時間上げすぎたため、装置内の圧力が上がって吸引できなくなり、血液は循環不全の状態となったとしています。圧力が上昇したら、装置についた弁を操作して圧力を下げなければなりませんでしたが、医師らはその操作方法を知りませんでした。また、落差法ではポンプの回転を上げても装置内の圧力が上がることはないため、医師らは原因がわからず、対処できませんでした。
- 京都府宇治市の宇治徳洲会病院(増田道彦院長)で1月末、心臓病で入院していた男性患者に看護婦が薬と間違えて毒物のアジ化ナトリウムを渡し、服用した男性が翌日死亡していたことがわかりました。アジ化ナトリウムは、尿検査で尿中の細菌増殖を防ぐために使っていました。病院側の説明によると、1月31日午後6時半ごろ、休憩室で休んでいた看護婦に、病棟補助者が尿検査に使うための紙袋に包んだアジ化ナトリウム約1.5グラムを渡しました。看護婦はその包みを服用薬と間違えて男性に渡しました。男性は服用後、容体が急変し、翌日朝、死亡しました。看護婦に薬を渡す際、病棟補助者は「ここに置いておきます」とテーブルの上に薬を置き、そのまま部屋を出て行ったということで、包みには薬品名などは書いておらず、伝票などもなかったということです。大阪府内の総合病院看護婦長は「毒物や劇物は医師の印鑑のある書類で受け渡しをするのが普通。かぎをかけた場所に保管するよう保健所の指導があり、机の上に置きっぱなしなんて考えられない」といっています。
- 腎臓病治療のための人工透析に伴う医療事故が、2000年に少なくとも2万1457件起き、うち372件は患者の生命を脅かすような重大な事故だったことが、厚生労働省研究班(班長・平澤由平・前日本透析医会会長)のアンケート調査でわかりました。血管に空気が入るなどで2人が死亡していました。回答したのは透析を実施する全国の医療施設の約半数です。透析患者のほぼ4人に1人が何らかの事故に遭った計算になります。研究班はこの結果を受け、透析用機械から抜けにくい構造の針を使う、機械に残った血液を患者に戻す際は空気圧でなく生理的食塩水を使う、などを定めた事故防止マニュアルを作成。全国の透析医療施設に配布しました。
- 検察官が容疑者の刑事責任能力の有無を判断するため起訴前に行う簡易鑑定の運用実態(2000年)が、毎日新聞の調べで初めてわかりました。大都市圏の地検に限っても、(1)精神科医1人当たりの診断者数に最大で25倍の格差(大阪128.5人、福岡5.1人)(2)精神障害者と認定される割合には最大で約50ポイントの差(大阪92.2%、京都41.9%)(3)精神障害者と認定された人の中で不起訴とされた割合にも約60ポイントの開き(京都95.5%、大阪33.8%)、などのばらつきが判明しました。
- 関西医大病院(大阪府守口市)の研修医森大仁さん=当時(26)=が急性心筋梗塞で死亡したのは過酷な勤務が原因として、大阪府堺市の両親が同医大に約1億7200万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁の坂本倫城裁判長は、勤務と死亡との因果関係を認め、同医大に約1億3500万円の支払いを命じました。原告側の岡崎守延弁護士によると、裁判所が研修医の過労死を実質的に認定したのは初めてです。判決理由で坂本裁判長は、死亡前2カ月半で月平均300時間を超えるなど長時間勤務があったと認定。「過重な研修で疲労、ストレスが増大し、心臓機能を著しく悪化させた。大学側が健康管理に細心の注意を払っていれば研修医の異常に気付くことができたのに怠った」と結論付けました。
- 厚生労働省は、学会が認定した専門医がいるかどうかや病気ごとの手術件数、受診患者数、セカンドオピニオンへの協力体制など、新たに医療機関が広告できる項目を決めました。一般に意見を募ったうえで大臣告示を改正し、4月から実施します。治療方法や学会認定専門医、手術件数など、治療の質や成績にかかわる情報が広告できるようになるのは初めてです。
- 「自宅で死にたいから救急車は呼ばない」「病院には行くが心肺蘇生は受けない」など、死に方をあらかじめ選んでおけるカードを、静岡市医師会が在宅患者に配っています。希望しない延命処置や救急車の不要な出動を避けるのがねらいです。1998年に始め、重い病気で寝たきりのお年寄りを中心とした市内の在宅患者のうち、4割近くに普及しています。カードは、家で死にたい人の「グリーンカード」と、救急車で総合病院に運んでほしい人の「イエローカード」の2種類。患者が、往診しているかかりつけ医や家族と相談して作ります。A4サイズで病状、投薬データ、かかりつけ医の連絡先、緊急時の連絡方法などが記入されています。「グリーン」を持つ患者の容体が悪化したら、家族はまず、かかりつけ医に電話する。連絡がとれないときは、市消防本部に通報。本部は救急車でなく、医師会が決めた当番医に連絡し、医師はタクシーで駆けつけます。「イエロー」は、市内4カ所の総合病院のうち一つを指定しておくと、急変時は救急車がそこに運びます。緊急時の治療法は、次の4つの選択肢から選んでおきます。(1)生死にかかわる緊急時にも心肺蘇生をしない(2)心肺蘇生術を含め積極的に治療することを希望(3)治療方針を主治医と相談したが結論は出ていない(4)今後の治療方針はまだ十分考えていない。受け入れる総合病院にもカードの控えがあり、患者の病状や希望がすぐわかります。1998年に始めたグリーンカードは現在132人、イエローカードは2000年からで193人が持っています。同医師会在宅医療協議会長の石井令三医師は「かかりつけ医と病院の連携が第一の目的だが、生前に家族で死に方を話し合ってもらうきっかけにもなる」と話しています。
- 子供が自宅から遠い病院に入院した時に、付き添う家族が宿泊できる施設「ドナルドマクドナルドハウスせたがや」(せたがやハウス)が昨年12月、東京都世田谷区の国立大蔵病院の隣接地にオープンしました。経済的負担の少ない宿泊施設を求める親たちの声に応え、日本マクドナルドのマクドナルド財団《http://www.dmhcj.or.jp/》
が創設したもので、建設から運営までトータルに手がける民間初の試みです。病院(国立成育医療センター)隣接で1泊1000円。共有スペースには、調理器具や冷凍冷蔵庫などを完備したキッチンコーナーが6世帯分並んでいます。マクドナルドハウスは、1974年米フィラデルフィアで白血病の娘を持つ親がハウス建設のために呼びかけた募金活動が発端。病院内のマクドナルドがシェイクの売り上げを寄付したことなどをきっかけに、マクドナルドハウス第1号は誕生した。現在、全米で約150、世界で213ハウスにまで広がっています。財団は2004年度までに、宮城県立こども病院、大阪府吹田市の国立循環器病センター、高知県立高知医療センターの3カ所でハウスの建設を予定しています。
- 小学4年の健康診断で行われている色覚検査が03年度から廃止されます。文部科学省が学校保健法施行規則の改正案をまとめました。色覚異常は遺伝子の変異のため、色の見え方が通常より少し異なります。日本人では男性の4.5%、女性の0.2%の合わせて約300万人。大半は生活に支障がありません。学校での一律検査が、進学や就職などで不利益を受ける「色覚差別」につながってきた、との指摘があり、日本色覚差別撤廃の会などが廃止を訴えていました。文科省学校健康教育課は「検査の目的は児童の学校生活に配慮することだった。だが、日常の不便がほとんどなく、見やすい教材の採用などの方がより適切なので、廃止を決めた」と話しています。厚生労働省も昨年秋、労働安全衛生法に基づき、会社側に義務づけていた新入社員の健康診断時の色覚検査を廃止しています。
- 英BBC放送は、高齢者や貧困者などが無料か割引料金で治療や処方薬を受けることができる英国民医療制度(NHS)が、アルコールや麻薬の中毒患者急増で危機に陥っていると報じました。アルコールの乱用が毎年30億ポンド(約5700億円)ものコスト押し上げ要因になっていると専門家は指摘しています。
▲ 目次にもどる
社会・その他
- 25歳以上の米国人の8割は太り過ぎで、6割が減量を実現できたらと思っているという実体が、米調査会社ハリスが発表した調査でわかりました。今回調査では80%が「過体重」とされる体格指数(BMI)25以上。この割合は1983年には58%でしたが、90年に64%、95年には71%に上昇していました。調査は今年1月16〜21日、約1000人を対象に実施されました。
- 「がん生存者」を対象とした大規模な調査を、厚生労働省の研究班が今秋にも始めます。がんを克服したり、通院で治療を続けたりしながら社会生活を送っている人たち1万〜2万人にアンケートし、再発への不安や社会的差別などの実態を探り、「生存者」の心と体をケアする支援システムづくりにつなげます。研究班によると、がんと診断されてから5年未満の「短期生存者」は全国に115万人、5〜25年の「長期生存者」は161万人いると推定されます(99年末時点)。合わせて270万人を超す「生存者」の生活実態は、ほとんど知られていません。
- テレビの「健康番組」が視聴率を伸ばしています。番組を書籍化すれば、ベストセラー。生活情報番組も健康問題をテーマに取り上げれば、視聴率がはね上がる傾向が続いています。人気番組は、いずれも中高年の女性を主なターゲットに、「健康な人をより健康に」が番組制作のコンセプトになっています。
- 学校給食用として大阪府内の小中学校などに毎日卸されている牛乳約55万本(1本200cc)のうち少なくとも約2万本(約4000リットル)が、手つかずのまま残されていることが府などの調査でわかりました。卸元の乳業会社が回収し、排水処理をして廃棄しています。
- 大阪府は「福祉のまちづくり条例」を改正、新たに建設される延べ1万平方メートル以上の大規模公的施設や民間ビルなどに、オストメイト(人工肛門や人工ぼうこう保有者)対応トイレの設置を義務付ける方針を固めました。9月府議会で条例改正し、03年4月以降の建築確認申請から適用します。対象は医療施設、官公庁、店舗、文化施設と全遊園地。車椅子トイレに温水シャワーと水槽を設け、設置しない場合は建築申請を受理せず、違反者は企業名を公表します。障害者団体の日本オストミー協会(本部・東京都)によると、オストメイトは全国9万2000人、大阪府内約4700人います。
- …アメリカでは、結婚してもすぐに離婚する若者が少なくない。60組の離婚カップルにインタビューしたパメラ・ポールは、「結婚にロマンティックな理想を追い求めるあまり、現実を見ていない」と分析する…「若者が結婚にうぶなのは社会の責任?」 <カティー・ロイフェ>《http://journal.msn.co.jp/articles/nartist2.asp?w=117702》
- 和歌山県高野町の高野山真言宗金剛峯寺と、福井県永平寺町の曹洞宗永平寺が、「二十一世紀を人類の希望の世紀とするため、平和と共存、共栄を考える対話を始めるべきだ」とする「高野山声明」を発表しました。両本山が交流するのは初めてで、今年5月には永平寺を開いた道元の没後750年の法要を高野山でも行い、人的交流も進めるということです。
- …世界で最も豊かな日本と、最も貧しいアフガン。その両国の商人が、中国の同じ田舎町に集い、同じ商品を同じ価格で買い付けている…「中国発、世界永久デフレの衝撃」 <日経ビジネス>《http://biztech.nikkeibp.co.jp/wcs/show/leaf?CID=onair/biztech/biz/172490》
▲ 目次にもどる
詳しい情報をお知りになりたい方は、何月号のどの記事かを明記の上、オーリング文化センター設計室<oring@baobab.or.jp>にメールして下さい。個人的に可能な範囲で対応させていただきます。
- ● 目次にもどる
- ● 情報クリップエッセンス・バックナンバー
- ● オーリング健康情報館
 電子版オーリング文化センター総合案内所へ
電子版オーリング文化センター総合案内所へ
記載責任者: 山本重明 Shigeaki
YAMAMOTO